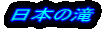

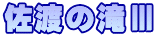 2025.7.8更新
2025.7.8更新
佐渡の滝
川を遡行していると、大なり小なりいくつかの滝が現れ、行く手を阻む。
国土地理院が定める滝の定義は、高さ5m以上となっているが、一般的には3mくらいでも滝と呼んでいる。
釣り人には厄介な滝だが、滝壺は大物の潜むポイントでもあり、滝の上にも更なる大物がいるのではと期待が
膨らむ。
佐渡には145もの二級河川があるので滝は多く、沢登りをする人にとっても格好のターゲットとなっている。
また、滝は被写体としても人気があるので、佐渡でも多くのアマチュアカメラマンが滝を訪れている。
藤津川で出会ったH老人もその一人で、自宅を訪ねた際にはたくさんの滝の写真を見せてもらった。
竹田川 夕栗の滝
畑野村志には「夕暮の滝」とあるが、藤津川で出会った三宮のH老人は、夕栗は地名なのだと教えてくれた。
前回は川沿いを通って夕栗の滝まで行ったが、途中からちゃんとした滝への道があることを、今回初めて知った。
川に下る道との分岐に、ピンクのマーキングテープがあったので分かったが、滝を訪れる人が多いのだろう。
国土地理院の地図に、林道から滝へと下る道の途中から、滝の上部へ繋がる破線があるのがずっと気になって
いた。
GPSを頼りに少し進んで見たが、道はあるようで無いような。
杉林の手前にお墓らしきものがあったが、経塚山登山口の奥にある一軒の民家(廃屋)のものだろうか。
2022.3.22
| 夕栗の滝 竹田川上流にあり、落差は25m |
この上にも3つの滝がある |
国府川 黒滝
かつて野生の朱鷺が生息していた黒滝山の近く、国府川の源流にある滝。
2段の段瀑で落差は15mとあるが、下からはそんなにあるようには見えない。(滝ペディアには11mとある)
昭和55年3月にこの滝を直登しているが、上段がどんなだったかまったく記憶にない。
2022.3.21
 |
|
| 黒滝 倒木は3年前から引っ掛かったままだ 増水してなければ上段の滝まで確認できたのだが、下から見る限り落差15mには見えない |
2段の段瀑 昭和55年3月にこの滝を直登しているが、上段がどんなだったかまったく記憶にない |
戸中の三滝
戸中の集落を通った時、道路からすぐ滝が見えたので立ち寄って見た。
落差25m程の段爆で、三滝とか権六滝と呼ばれている。
滝のある戸中川は小さな川なので、水量の多いこの時期ならでは滝なのかもしれない。
2022.3.17
| 戸中川にある三滝 落差25m |
上部がよく見えないが、3、4段からなる段爆のようだ |
真更川大川の滝
本流下流に滝らしいものが見えたが、はっきりとは確認できなかった。
上流は滑床の多い平坦な川で滝らしいものは見当たらなかったが、支流の沢から流れ落ちる滝は、この時期
だけに見られるものだった。
2022.3.19
| 支流の沢から流れ落ちる滝 雪解けの頃にしか見れない滝だ |
上流にある滝 落差は3m程 |
古川(こごう)の滝
内海府の古川上流にある。
河口から900m程進むと、両岸が切り立ったゴルジュの先に2段の段瀑が現れる。
水量が多くてとても近づけず、下段と上段でどれくらいの落差があるのか下からでは分からなかった。
2022.3.19
| 河口から900m程の所にある | 支流の滝 水量が多いので立派な滝に見える |
小倉川の滝
小倉四十八滝と呼ばれる滝があるそうだが、祓川の滝が含まれるのかどうかは分からない。
どこまでを滝として捉えているのかにもよるが、祓川には大小含め滝と呼ぶに相応しい滝がたくさんある。
昨年祓川左俣のF2を越えられず完全遡行が敵わなかったので、再び飯出山登山道から下降して滝を調査した。
小倉トンネル手前の七福神の広場に車を止め、まずは飯出山登山口から標高480mのピークまで登る。
前回はここから二俣の右側の沢に下りたが、今回は高低差120mの枝尾根を下って滝上に出るショートカットを
選択。
途中大きな岩に行く手を阻まれたものの、ガレ沢を慎重にトラバースし川に降りた。
ここで登山靴から渓流タビに履き替え、川を下りながら滝の調査を開始。
| 上から1番目の滝 落差は4m程 |
2番目の滝 上部の小さな滝を含めれば、3段5mの滝と言ったところ |
| 3番目の滝 落差は4m程 |
4番目の滝 これも上部の小さな滝を含めれば、3段5mの滝と言ったところ |
| 5番目の滝 落差は3m程しかないが形のいい滝だ |
6番目の滝 落差は3m程 |
前回は7番目の滝までしか行くことが出来なかったが、今回の調査でその下にも3つの滝があることが分かった。
8番目と9番目の滝は右岸を高巻いて下降したが、結構危ない場面もあり、帰りはスワミベルトと20mロープを取り
出し懸垂下降で突破した。
10番目の滝は落ち口からしか確認できなかったが、降りるには相当大きく高巻かなければならず、今回はここで
終了。
F1、F2と合わせれば左俣には12もの滝があることになるが、10番目の滝の下にもあと2つくらいあるような気もした。
すべてを調査するにはF2突破が絶対条件なので、難易度は高いが来春にでももう一度挑戦してみたい。
2021.10.28
| 7番目の滝 下まで含めれば落差10mはあるかも |
8番目の滝 上部の小さな滝2つを含めれば、4段7mの滝と言える |
| 9番目の滝 正真正銘滝と呼べる滝で、落差は5m程 左岸に腐りかけた残置ロープがあった |
10番目の滝 落ち口から見たところ、落差は4m程だった |
養老の滝
岩首川上流にある2段の段瀑で、落差は29mとある。
岩首の棚田とセットで見に行けるので、島外から訪れる人も多く、観光スポットになっている。
| 岩首川にある養老の滝 2021.9.12 |
2段の段瀑で落差は29mとある |
| 2012年に訪れたと時のもの | 2012.7.24 |
鍋倉の滝
旧畑野町大久保の真禅寺にある滝で、鎌倉時代に佐渡に流された文覚上人が修行した滝と言われている。
2004年に訪れた時はなかったが、今は岩の上に上人の石像が乗っている。
落差が10mとあるが、見た感じ7、8mといったところか。
2021.9.18
| 文覚上人の石像 2004年に訪れた時は木の看板だけだった |
落差10mとあるが、見た感じ7、8mといったところか |
張骨沢不動滝
片辺越えで金北山を目指す途中に立ち寄った。
不動滝は張骨沢の出合いにあり、更に上流には七つ滝があるが、全貌はまだ掴めていない。
| 2021.9.13 | 不動滝の更に上流には七つ滝がある |
小河内川七ツ滝(ななつがたき)
佐渡屈指の名瀑で、落差が7段100mもあると言われる小河内川の七ツ滝に挑戦した。
藤津川で出会ったH老人も絶賛していたが、自宅で見せてもらった滝の写真は見事で、一度は訪れたいと思って
いた。
小河内川は大河内川の支流だが、大河内川の二級河川としての名称は大川になっている。
真更川にも大川があり、両津にも大川があるので、それらと区別するためか岩谷口大川とも呼ばれている。
七ツ滝はまずF1、F2を右から巻いてF3に出た。
F3は左を直登しF4に出られるようだったが、疲労で足がおぼつかない状態だったので、ここまでで終了した。
登った人の記録では、落差はF1~F4で20m、F5~F7で80mの、合計7段で100mとのことだった。
11月か3月頃ならF6、F7辺りまで見えるようなので、機会があればまた訪れて見たい。
2021.9.11
| F1、F2 | F3、F4 |
| F3 疲労困憊で余力なく危険だったので、これ以上上るのは止めにした |
F4 左奥にF5より先の滝が微かに見えるが、木の葉が茂っていて良く見えない |
| 魚止めの滝 | 支流の滝 |
法力和光滝
林道石名-和木線からの入口が分からなかったので、和木川を下から遡行してやっと辿り着くことができた。
探しても分からなかった入口は、標高570m地点、石名天然杉まで3㎞の先にあり、今は入口に看板が設置され
ている。
2段の段瀑で、落差は20m程はあるだろうか。
| 2021.6.16 | 2021.7.17 |
北狄川支流 岩山川の滝
発電所跡から600m程上流にあり、落差は3mくらいしかないが、魚止めの滝の雰囲気がある。
この下にも3mの滝があった。
2021.5.13
北狄川支流 下山川の滝
取水口跡から100m程上流にあり、落差は10m以上はありそうだった。
| 2021.5.13 |
戸地川右俣魚止め滝
手前に通らずの淵があるので右岸の斜面から覗いてみたが、この滝を攻略するのは難しそうだ。
高巻いて下に下りたとしても、一段目から先に進めない感じだ。
小さな滝も含めて全部で七段あると言われている。
| 2021.3.27 |
全部で七段あるらしい |
戸地川支流小俣沢魚止めの滝
めがね橋のすぐ上にある滝で、落差は3m程か。
このくらいの落差ならば魚は遡上できそうだが、滝より上でアタリはなかった。
2016.8.16
戸地川支流小俣沢上流の滝
魚止めの滝から500m程進んだ所にある滝で、落差は10m程と記憶している。
右岸にフィックスロープがあったが、かなり古いロープなので、これを信じて上るのは危険だろう。
廃止された戸地川第一発電所の放水路跡が、ヘッドタンクのあった場所から小俣沢に下りていたようなので、
そこから下れば滝の上流に出られるのかもしれない。
| 小俣沢の滝 2016.8.16 |
滝は左の直角に曲がった所にある |
滑滝
大ザレ川の上流は滑床の多い川だった。
一般的に滑床は岩魚が居つかない場所なので、竿を出しても無駄だと思っていた。
左沢の滑滝が連続する窪みに岩魚が居たのは新たな発見だった。
大ザレ川左沢の滑滝
大ザレの滝
県道沿いにある柿畑の横に海に下る道の入口があり、そこから海までは100m程下る。
更に海岸を500m程歩かなければならないが、石がゴロゴロとしていて歩きにくい。
柿畑から滝までは20分、帰りは30分も掛かった。
落差は70mと言われているが、実際に滝を登った人の記録を見ると、2段目の滝F2を合わせても48m程らしい。
| 大ザレの滝と海府大橋 |
落差は40m程 2021.3.23 |
白布の滝
「中川の上流字白布にあり、懸泉数丈の断崖を下る処白布をさらせるが如し、此名ある所以なり」
畑野村志より
旧畑野町小倉地区西ヶ平にある白布(しらふ)の滝。
その存在自体は前々から知っていたが、林道からの入口が分からず、まだ行ったことがなかった。
行った人のブログを見ると、水路沿いに道があり簡単に行けそうだったので、タウンシューズで出掛けたが、
結局入口が分からず、手は切るわ、レンズキャップは失くすわで散々だった。
西ヶ平は実家から15分も掛からないので、ちょっと出掛けてくる感覚だったが、やっぱり滝への入口が分からない。
結局荒れた林道を暫く進み、林道横に車を止めて、斜面から川に下りるしかなかった。
そこから川沿いを歩き、やっとのことで滝に辿り着いたというわけだ。
(帰りになってやっと入口が分かったのだが...)
2021.3.22
3日後、再び白布の滝を訪れた。
失くしたレンズキャップの捜索がてら、今度は渓流タビを履いて水路沿いに行って見ることにした。
水路沿いの道はよく整備されており、途中からは川沿いを歩くことになるが、渓流タビなので川の中も平気だ。
結局レンズキャップは見つけることができなかったが。
2021.3.25
| 二段の段爆 2021.3.22 |
落差は20m程 2021.3.25 |
新保川支流 張骨沢七つ滝
張骨沢は新保川の支流で、七つ滝を目指すには出合いの不動滝を巻くか、片辺ルートから下降する何れかになる。
不動滝は張骨沢の出合いにある落差10m程の滝で、かつて右岸を高巻きして七つ滝を目指そうと試みたことが
あるが、下降点が見つけられず断念していた。
今回は片辺ルートから下降して、七つ滝を目指すことにした。
又次郎川内沢を横切り、ミズナラの巨木がある開けた場所まで登ったが、道は結構荒れていて何度か見失いそう
になったが、ピンクのマーキングテープを探しながら進んだ。
ミズナラの巨木のところから小さな沢沿いに下り、急斜面を慎重にトラバースしながら張骨沢の河原に降り立った。
直ぐに現れた2m滝を左岸から高巻き、更に50m程進むと、目の前に落差が10m以上はありそうな滝が姿を現した。
これが七つ滝の最初の滝だが、左右見渡しても、右岸も左岸も巻けそうなところがない。
取り敢えず少し引き返し、左岸の涸沢を登ってみたが万事休す。
右の斜面に取り付き、開けた場所まで戻ることにした。
高巻きの途中、最初の滝の上にすぐ2番目の滝が見えたが、ここまで行くには難易度がかなり高そうだ。
もう少し作戦を練ってから再チャレンジすることにし、張骨沢を後にした。
| 2020.11.12 | 落差は10m程 |
小倉川支流 祓川の滝
前回巻けなかったF2を、右岸斜面を木の枝に掴まりながら巻いてみようと、急斜面を慎重にトラバースしなが
ら進む。
太めの木の枝にシュリンゲでセルフビレイしながらルートを探り、あともう少しというところまできたが、枝と枝
と間隔が広くなり、にっちもさっちもいかなくなった。
滑落のリスクが高いので強硬突破するのは諦め、20mロープを取り出した後、斜めに懸垂をしながら急斜面を
下りた。
今度は大きく高巻こうとガレ場を直登してみるが、30m、40mと高度を上げていっても、右側には直立した岸壁
がずっと上まで続いていて、巻けそうな場所がない。
F2のすぐ上に滝が見えたが、先日見た滝かどうが判別がつかず、無念の敗退となってしまった。
| F1、目測5mとしていたが、実測は8mあった 2020.11.14 |
F2、5m以上はありそうだ 2020.11.12 |
祓川左俣上流の滝
飯出山登山道を標高480mのピークまで進み、左側のやや緩やかな斜面を高低差80m程下ると、二俣に分かれた
右側の沢に出る。
更に沢を100m程下ると二俣の左側の沢と合流した。
二俣から300m程下ると、小さな滝が次々と現れ、標高330mの地点で10m程の緩やかに流れるような滝が現れた。
これが登山道から見えた滝で間違いないようだ。
帰りは左岸の涸沢を直登して標高460m付近の登山道に出た。
高度差130mの直登は結構しんどいものがある。
祓川左俣上流の滝 2020.11.8
| 川を下ると3m程の滝が現れた。 | これも3m程の滝 |
上流から4番目の滝 |
祓川右俣の滝
飯出山登山道の途中、標高290mラインの右側から繋がる水路跡を進むと、30分程で右俣の滝が現れる。
道は枝をかき分けて進まなければならないほど荒れてるが、川を遡行するよりは遥かに楽だ。
祓川右俣の滝 2020.11.8
白瀬川の滝
右俣(馬の瀬川)の滝
東北電力の方に沢の名前は教えて頂いたが、滝の名前までは分からないと言う。
これだけ大きな滝だから、きっと名前はあるのだろう。
| 落差20mはありそうだ。 | 2020.7.20 |
| 本流3mの滝 2020.7.20 |
左俣(御林沢川)取水口下の滝 2020.7.20 |
| 中俣(大平川)F1、2段3mの滝 2020.7.13 |
中俣(大平川)F2、3mの滝 2020.7.13 |
張骨沢不動滝
ずっと10m程としていたが、よく見るとそれ以上はありそうだ。
藤津川で出会ったH老人は、シラネアオイの花の背景に不動滝を入れた写真が、今まで撮った滝の写真の中でも
一番のお気に入りで、機会があればもう一度撮ってみたいとも話していた。
2020.6.3
新保川本流F1、5mの滝 2020.6.3
和木川の滝
右俣を標高650m付近にある法力和光滝まで詰め、林道石名-和木線で戻る計画を立てたが、標高500mを過ぎた
あたりから沢は険しくなり、標高580mの所で落差が15m程ある滝が現れた。
左岸を巻こうと途中まで登っては見たが、斜面はズルズルで、掴まるものもなかったため、残念ながら法力和光滝
まで辿り着くことは叶わなかった。
| 右俣F1、3mの滝 2020.6.5 |
右俣F2、15mの滝 2020.6.5 |
石花川ブイガ沢の滝
滝をどう巻こうか考えていたが、直登できそうだったので途中まで登って見たが、上部がヌルヌルで結構危なかった。
滝から上も小さな滝が連続し、標高280m付近で引き返し、標高330m付近にある取水口跡まで行くのは諦めた。
石花川ブイガ沢5mの滝 2020.6.8
梅津川水川内沢の滝
ドンデン山に続くアオネバ渓谷の登山道沿いから見える滝。
佐渡汽船のジェットフォイル内で流される、観光案内のビデオに出てくる滝だ。
水川内沢3mの滝 2020.6.17
入川の滝
入川の右岸から流れる小さな沢にある滝で、トンデン山に続く佐渡縦貫線を登って行くとすぐ左脇に見える。
国土地理院の地図を見ると、沢はすぐ二俣になっているようだ。
等高線がかなり詰まっているので、多くの滝が見られるかもしれない。
左岸の支流白滝川にはまだ入ったことはないが、水路跡を辿っていくと大きな滝があるそうだ。
| 2019.6.20 | 2020.6.12 |
本流上流の取水口跡にあるのは堰堤だと思っていたが、よく見ると滝のようにも見える。
落ち口の部分がコンクリートの取水口になっていたのでそう思っていたが、下の部分は自然の岩のようにも見える。
2020.6.12
| 落ち口の部分はコンクリート造りになっている 2019.6.20 |
孫次郎川へ続く水路跡方面から 滝のようにも見える |
泊川の滝
県道のすぐ脇にある泊川5段の滝。
落差は30m程あるそうだが、下からだと5段あるのが分からない。
泊川は2級河川にも準用河川にも分類されていない。
| 泊川の滝 2020.3.12 |
2020.6.2 |
鍋倉の滝
旧畑野町大久保の真禅寺にある滝で、鎌倉時代に佐渡に流された文覚上人が修行した滝と言われている。
写真は2004年に訪れた時のものだが、今は看板のある岩の上に上人の石像が乗っているようだ。
落差がどれくらいだっか記憶がないが、見た感じ10m程だろうか。

鍋倉の滝 2004.5.2
お滝
坊ケ浦から長谷に向かう道路沿いにあり、昔は修験者の行場になっていた。
長谷の集落から流れ出たゴミが散乱していて、他の滝のように綺麗な滝ではない。
中学生の頃(畑野中学校)は、お滝まで行って帰ってくるのがの部活のランニングコースだった。
落差は6mとあった。
お滝 2018.11.11
藤津川の滝
藤津川ダムのバックウォーターから黒滝までを1年ぶりに遡行した。
最初のF1、5mとF2、5mは、F1の右岸手前から大きく巻き道があり、F2の上部に抜けられる。
白滝は右岸の斜面を10mほど直登しなければならないが、滑落しないよう木の枝に掴まりながら慎重に登った。
黒滝からは、雪に埋まった道を尾根まで行き着く自信がなかったので、左岸手前の斜面を直登することに。
高低差は80m程だったが、木の枝に掴まり息を切らしながらも、やっとのことで地獄谷線に辿り着くことができた。
2020.3.4
| F1(5m)、奥に見えるのがF2(5m) |
F5(10m) |
F6(3m)、F6の奥に見えるのが白滝
白滝(15m)
高巻きの途中から見た白滝
黒滝(20m)
黒滝は下からは2段の滝に見えるが、高巻きの途中からは3段、もしくは4段の滝のようにも見えた。
4段目が独立した滝なのかどうかは判別できなかったが、昨年F9、5mから覗いた落口かもしれない。
高巻きの途中から見た黒滝
大ザレ川の滝
河口にある大ザレの滝は有名だが、上流にもいくつかの滝が存在するようだ。
今回は山居池から下降して、魚止めの滝F3、10mまでを調査した。
2020.3.12
| 魚止めの滝(2段10m) |
横から見た魚止めの滝 |
| 山居池下の滝(10m) | 本流F1(3m) |
本流F2(3m) |
| 枝沢の滝(10m) 奥に見えるのは20mの滝 |
枝沢の滝(20m) | 枝沢の滝(10m) |
石花川の滝
石花川には6つの支流以外にも小さな沢がたくさんあるので、滝も相当数あると思われる。
何れも険しい沢だけに、そう簡単には遡行できない。
| 長尾沢の滝(5m) 2020.3.9 |
|
| ブイガ沢の滝(5m) 2020.3.9 |
発電所跡上流300m左岸から流れ込む沢の滝(15m) 2019.3.18 |
| 2019.3.19 竹平沢の滝 手前の滝が10m、奥の滝が20mほど。 |
奥の滝、落差20m |
手前の滝、落差10m |
小倉川支流祓川の滝
小倉四十八滝と呼ばれる滝があるそうだが、詳しいことはよく分からない。
飯出山登山道からは今回の滝以外に何ヶ所かあることが確認できたので、機会があれば再度調査して見たい。
2020.3.6
左俣の滝(F1、5m)
左俣の滝(2m)
左俣の滝(F2、5m)
右俣の滝(F1、3m)
右俣の滝(F2、10m)
小倉川支流大久保川の滝
大久保川は小倉川の支流の一つで、猿八集落から経塚山に向かって尾根の右側が竹田川で、左側が
大久保川になる。
猿八の集落から800mほど上った所に落差15mほどの滝があったが、他にも何ヶ所かあるそうだ。
2019.3.12
不動滝
新保川には三段の滝や七つ滝などがあるが、何れの滝も近くまで行って見たことはない。
三段の滝は二箇沢(ふたさわ)の上流、七つ滝は張骨沢の上流にあるが、それなりの装備と覚悟がないと
行けない。
不動滝は張骨沢の出合いから数十メートルの所にあり、落差は10m程。
右岸を高巻きしようと試みたことがあったが、下降点が見つけられず断念した。
七つ滝は位置的には片辺ルートの標高650m~750mラインあたりになる。
過去に片辺ルートの650mラインまで行き、雪渓に埋まった沢にいくつかの滝が見えたが、これが七つ滝だと
思われる。
| 2018.5.22 | 2019.5.21 |
 |
|
| 本流の滝 F1、5m 2018.5.22 |
神子岩から見た張骨沢七つ滝 片辺ルートからも直下に2つの滝が見えた 2004.5.1 |
二箇沢の滝
二箇沢は出合いから100m程でF1、3mの滝が現れ、更にF2、3m、F3、10mと連続する。
ぱっと見ただけだが両岸とも切り立っていて、高巻けるような感じはしなかった。
上流に三段の滝があることは沢口コースの登山道から見て分かるが、どうやったらたどり着けるのかは
分からない。
2019.5.21
2019.5.21
 |
|
| 出合いから100m程でF1、3mの滝が現れる 2019.5.21 |
沢口コースの登山道から見た二箇沢三段の滝 2003.4.27 |
黒滝
藤津川には何ヶ所かの滝があるが、中でも黒滝と白滝は滝好きには名が知られている。
黒滝は林道地獄谷線から小尾根沿いに下って20分くらいの所にある。
かつては整備された遊歩道があったようだが、今は倒木などで荒れていて道はかなり不明瞭になっている。
この日上流で初めてH老人に出会い、行き方を教えてもらったおかげで何とか辿り着くことが出来た。
2019.5.13
| 落差は20mほどだが、末広がりの見事な滝だ |
上部は2段の段瀑になっているようだ |
白滝
黒滝のすぐ下流にある滝だが、ここも道が不明瞭で何度も迷った。
黒滝から一旦川沿いに下り、白滝の落ち口を右岸から植林地の中を通ると小さな尾根に辿り着く。
滝下まではおよそ15m程の高さがあり、木の枝につかまって下りるには急斜面過ぎて危ない。
安全のためスワミベルトと20mの補助ロープを取り出し、懸垂で滝下まで下りた。
2019.5.13
| 下流から遡行した時は、これが白滝だとは確信できなかった 2019.5.8 |
右岸を高巻いて枝尾根から上部に出れば黒滝に辿り着く |
藤津川の滝
黒滝、白滝以外にも藤津川にはたくさんの滝がある。
下流の藤津川ダム上流の堰堤から400m程でF1、F2が連続して現れる。
何れも落差は5m程だが、整った綺麗な滝だ。
更に白滝下流に4つと、黒滝上流に2つの滝がある。
2019.5.8
| 堰堤から400m程でF1、5mが現れる 右岸を小さく巻いてF2に出でたが、帰りはF2から大きく巻いて下った すぐ上に見えるのがF2、5m |
F2、5m これも右岸を巻く |
| F5、10m 上部にF6、3mが見える 左岸を巻いてF6へ |
F6、3m 直ぐ上に白滝が見える |
| F9、5m このすぐ下が大きな滝になっていたが、落ち口からでは確認できず 黒滝なのか、新たな滝なのかは不明 |
F10、10m 林道地獄谷線からすぐ川に下りるとF10があり、その下にF9がある |
夕栗の滝(ゆぐりの滝)
竹田川の上流、猿八にある滝で、落差25mの分岐瀑。
見ごたえのある滝で、アマチュアカメラマンを始め多くの人が訪れているようだ。
右岸の枝尾根を高巻いて上流を目指したが、すぐに5m、5m、10mと3つの滝が連続する。
10mの滝は右岸の枝尾根を高巻いて経塚山登山道に出ることができたが、更に上流にも滝があるようだ。
夕栗の滝の夕栗は地名なのだと、H老人が教えてくれた。
| 2018.11.10 | 2019.3.8 |
| 上が2段になっている 2018.11.10 |
高巻の途中、横から見た夕栗の滝 分岐瀑になっているのがよくく分かる 2019.3.8 |
| 夕栗の滝の上流にある5mの滝 すぐ奥に5mの滝が続く |
5mの滝 |
10mの滝 右岸を高巻き枝尾根から経塚山登山道に抜けた |
十郎滝
竹田ダムの下流にある滝で、佐渡では有名な滝の一つ。
国分十郎末俊が、年老いた母の病を治すため、毎夜この滝に打たれながら祈願したという親孝行伝説がある。
落差20mとあるがそんなに高くは感じない。
竹田ダムができた影響で土砂が堆積し、川底を上げてしまったのだとH老人は言う。
15m程と思われるが、水量が多い時期には爆風が凄く迫力はある。
2019.3.9
| 爆風が凄く迫力はある |
20mもあるようにはとても思えない |
平山の滝(たいらやまの滝)
かつて山女魚や岩魚の宝庫だった小倉川だが、ダム建設や護岸工事の影響で壊滅状態になってしまった。
滝だけは当時と変わらないのが唯一の救い。
小倉ダム(朱鷺湖)の駒の上大橋から300mほど上ったところにあり、看板はないが道はよく整備されている。
落差は20m~25mと、小倉川にある滝の中では一番大きな滝かもしれない。
| 2018.11.11 | 2019.3.24 |
| 離れて見ると上部が段瀑になっていることが分かる |
2019.3.24 |
大開の滝(おおびらきの滝)
小倉川の支流中川の西ヶ平にある滝で落差は10m。
中川もかつては山女魚や岩魚の宝庫だったが、川はコンクリートの護岸に変わり見る影もなくなった。
2019年3月に調査した時は魚影すら確認できなかった。
この滝のすぐ上流に白布の滝があるようだが、残念ながらまだ訪れたことはない。
| 2019.3.5 |
臼ヶ滝
新穂ダムから林道黒滝線を2㎞ほど進むと、やがて林道は二俣に分かれる。
右は黒滝に繋がる黒滝林道で、左が臼ヶ滝林道になるが、営林署のゲートがあり車は通れない。
臼ヶ滝はゲートから400mほど上ったところにある。
ずっと「白ヶ滝」だと思っていたので過去の地理院地図を引っ張り出して見ると、ちゃんと「白ヶ滝」と表記してあった。
最新の地理院地図は「臼ヶ滝」になっているので、「臼」を「白」と誤表記してしまったのだろう。
落差は8mとなっているが、実際は6mくらいだろうか。
佐渡にヤマビルはいないと思っていたが、新穂の山にはいるのだとH老人が教えてくれた。
そんな話を聞くと、もう国府川や大野川に入る気がしなくなってきた。
全国ヤマビル情報には入川や赤玉杉池あたりでも目撃されていると記載がある。
房総のヤマビルは鹿により拡散されてしまったが、佐渡も拡散が心配だ。
2018.11.11