日本の滝・名瀑~名もない滝
国土地理院が定める滝の定義は高さ5m以上となっているが、一般的には3mくらいでも滝と呼んでいる。
渓流釣りや沢登りの遡行図では、下流からF1、F2、F3...と表記。
滝にも種類があり、直爆、分岐爆、段爆、渓流爆などに分類されている。
秋保大滝
名取川の上流にある滝で、つり人社の「東北の渓流」には不動の滝と記載されている。
日本三大瀑布(名瀑)と言えば、那智の滝、華厳の滝、袋田の滝を指すのが一般的だが、東北地方では袋田の滝
の代わりに秋保大滝を日本三大瀑布と呼んでいるようだ。
確かに袋田の滝は他の二つの滝より知名度は劣るが、秋保大滝を三大瀑布に入れるのはどうかと思う。
高さ55mとあるが目測で見る限り25m~30mがいいところだが、異論を唱える書き込みは見当たらない。
佐渡の大ザレの滝も落差70mとか100mとか書かれているが、実際は40m~50mがいいところで、滝の高さ表示は
アバウトなものが多い。
幅6mとあるので、写真上の縦横比で計算しても、概算で25mという結論に達するのだがどうなんだろう。
(55mなら縦横比9:1になるはず?)
2024.10.26
 |
 |
| 滝見台から見た秋保大滝 落差55m? |
幅6mとあるので縦横比から見て落差55mには無理がある |
龍門の滝
那珂川支流の江川にある高さ20m、幅65mの大きな滝で、遊歩道が整備されているので滝下まで下りることが
出来る。
川自体はあまり綺麗ではないが、秋には鮭が上ってくるという。
| 龍門の滝 那須烏山市滝 |
遊歩道があり滝壷付近まで下りられる |
房総の滝
高い山がない千葉県にも滝はある。
水量が少ないので見劣りもするが、一雨降れば立派な滝に変身する。
山登りの帰りに立ち寄った滝をいくつかピックアップしてみた。
 |
 |
 |
| 坊滝 増間ダム上流にある落差25mの大滝 御殿山、大日山の帰りに立ち寄った 一雨降れば見ごたえがあるだろう (南房総市増間) |
四方木にある不動滝、落差10m 小櫃川上流の七里川渓谷の奥にある (鴨川市四方木) |
黒滝、落差15m 花婿街道沿いの長者川にある 烏場山からの帰りに立ち寄った (南房総市和田町花園) |
 |
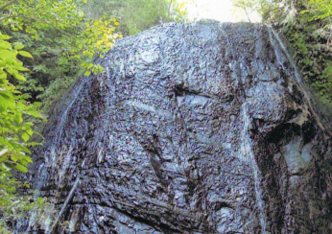 |
 |
| 白絹の滝、30m サテライト鴨川の手前を右に入ると白滝不動教会がある 嶺岡浅間の帰りに立ち寄った (鴨川市上小原) |
高宕の大滝、落差13m 高宕山の帰りに立ち寄った (君津市怒田沢) |
豊英の大滝 落差は7.5m、幅は20m 清和県民の森から奥に入ったところにある 笹郷山、川又大塚山の帰りに立ち寄った (君津市豊英) |
 |
 |
|
| 吉堀の滝 落差は10m程 チバニアンの帰りに立ち寄った (市原市国本) |
桃谷の滝 高宕山で道に迷い降りた沢にあった滝 (君津市怒田沢) |
田代滝 落差9.5m、幅15mとある (大多喜町田代) |
るり渓(瑠璃渓)
大阪は豊中の上新田に住んでいたので、箕面や能勢方面に出掛けることが多かった。
るり渓は京都府(南丹市園部町)にあるが、能勢町の隣なので豊中の自宅からは車で1時間と近かった。
渓谷沿いには遊歩道が整備されており、老若男女誰でもが渓谷美を楽しむことができる。
紅葉の名所としても有名だ。
るり渓へは2008年11月と2009年4月の2度訪れた。
近くには日帰り入浴できる「るり渓温泉」があり、タオルだけでなく混浴露天風呂用の水着まで無料で貸してくれる。
2008.11.30&2009.4.11
| 南丹市園部町にある「るり渓」 渓谷沿いに遊歩道が整備されている |
千幻瀑(せんげんばく)、会仙巖(かいせんがん) 12勝といってそれぞれに名前がついている |
欄柯石(らんかせき)、浣紗瀬(かんさせ) |
| 水晶簾(すいしょうれん) | 玉走盤(ぎょくそうばん) | 双龍淵(そうりゅうえん) |
| 渇きゅう澗(かっきゅうかん) | 鳴瀑(めいばく) | 紅葉の名所としても知られている |
有馬四十八滝
有馬四十八滝は六甲山地中腹の紅葉谷と白石谷にある滝群の総称で、冬季の氷瀑が人気スポットになっている。
大阪に勤務していた頃、2008年の晩秋に一度だけ有馬温泉から大谷川沿いに六甲山まで登った。
ロープウェイ有馬温泉駅の駐車場に車を止め、大谷川沿いに林道を進むと20分で白石谷出合いに到着する。
白石谷コースはベテラン向きなので、極楽茶屋跡を目指す紅葉谷コースを選択した。
七曲滝分岐に難所ありの表示があるも、固定ロープがあり慎重にトラバースして通過する。
蟇滝(がまたき)と七曲滝を見た後再び七曲滝分岐に戻り、歩くこと10分で百間滝分岐に到着。
油断すると滑落の危険もありそうな道を一気に下ると百間滝だ。
似位滝(にいのだき)も見て再び分岐へ戻ると、後はひたすら頂上を目指すだけだが、これがけっこう辛かった。
極楽茶屋跡から六甲ガーデンテラスまで行き、帰りはロープウェイで有馬温泉に戻った。
2008.11.22
| 晩秋の紅葉谷コースを進む 2008.11.22 |
蟇滝(がまたき)落差8m | 七曲滝 |
| 七曲滝は落差30mとある | 百間滝 | 百間滝も落差30mとあるが |
| 似位滝(にいのだき)も落差30mとある | 有馬温泉方面を振り返る | 極楽茶屋跡(標高866m)から大阪湾を望む |
コースタイム
ロープウェイ有馬駅11:55-白石谷出合い12:15-七曲滝分岐12:25-七曲滝12:30-七曲滝分岐12:40-
百間滝分岐12:55百間滝13:00-似位滝13:05-百間滝分岐13:15-極楽茶屋跡13:45
1時間55分
有馬温泉には日帰り入浴できる「金の湯」があり、強塩泉のため鉄分が酸化して赤茶色に濁っているのが特徴。
かなり熱い温泉だったと記憶。
また有馬温泉駅近くにある有馬ラーメン「青龍居」も人気の店。
奥多摩の滝
沢を遡行するのは好きだが、本格的な沢登りは年齢的にも技術的にも無理がある。
危険を冒してまで挑戦する理由もないのだが。
沢屋は滝を直登するが、釣師は敢えて直登する必要はなく、高巻きできれば十分だ。
奥多摩には沢がたくさんあるが、1級から2級の沢が多く、初級レベルの自分でも何とかなった。
今までに峰谷川支流の入奥沢、坊主谷や小中沢、後山川支流片倉谷、シダクラ沢、入川谷、熊倉沢、小坂志川
など、初級レベルの沢をチョイスし遡行した。
| 峰谷川支流カタサメ沢の大滝 2016.2.21 |
峰谷川支流入奥沢5mの滝 2016.2.21 |
小中沢5mの滝 2016.5.4 |
 |
||
| 小中沢5mの滝 2016.5.4 |
後山川支流片倉谷10mの滝 2016.7.31 |
片倉谷3mの滝 2016.7.31 |
| 入川谷支流布滝沢布滝15m 2018.7.22 |
入川谷3mの滝 2018.7.22 |
入川谷外道滝5m 2018.7.30 |
| 入川谷銚子滝8m 2018.7.30 |
シダクラ沢2条4mの滝 2017.7.22 |
シダクラ沢2段6mの滝 2017.7.22 |
| シダクラ沢ハング滝3m 2017.7.22 |
シダクラ沢トイ状の滝5m 2017.7.22 |
南秋川熊倉沢西沢2段7mの滝 2017.5.5 |
| 熊倉沢西沢チョックストーン滝3m 2017.5.5 |
熊倉沢東沢トイ状の滝 2017.5.5 |
熊倉沢東沢5mの滝 2017.5.5 |
| 熊倉沢東沢2段10mの滝 2017.5.5 |
南秋川小坂志川3mの滝 2019.7.27 |
小坂志川キットウ谷沢5mの滝 2019.7.27 |
| キットウ谷沢左俣の滝 2019.7.27 |
キットウ谷沢右俣出合の滝 2019.7.27 |
キットウ谷沢右俣10mの滝 2019.7.27 |
スッカン沢の滝(栃木県那須塩原市)
スッカン沢は箒川の支流鹿股川の上流にあり、多くの滝があることから、冬に凍結した滝を見に来る人も多い。
本格的に凍るのは2月頃。
鹿股川は上流で右岸から桜沢が出合い、本流はスッカン沢と名前を変える。
桜沢はナメ床と大岩が目立つ沢で、雷霆(らいてい)の滝と咆哮霹靂(ほうこうへきれき)の滝がある。
 |
 |
 |
| 雷霆(らいてい)の滝(2段の段滝落差10m) |
咆哮の滝(2段の段滝落差12m) |
霹靂の滝(落差12m) |
 |
 |
 |
| 霹靂の滝 |
雄飛の滝(落差10m) |
仁三郎(にざぶろう)の滝(落差7m) |
氷瀑・氷柱
百尋の滝
奥多摩の川苔山への登山コースの途中、川乗谷の上流にある落差40mの滝。
2017.1.15
スッカン沢
那須塩原にあるスッカン沢の氷柱も見事だった。
2019.1.12
 |
 |
 |
 |
粟又の滝(千葉県大多喜町)
養老渓谷にある粟又の滝は千葉で最も有名な滝で、新緑や紅葉シーズンには多くの観光客が訪れる。
滑り落ちるように流れる落差30m、幅30m、延長100mの滝は見事だ。
落差30m、幅30mの滝、延長100m 2018.12.1
2015.12.13
濃溝の滝(千葉県君津市)
SNSで一躍有名になった濃溝の滝こと亀岩の洞窟は、君津市の小櫃川の上流にある。
川廻しによって人工的に掘られたもので、房総の川ではよく見られる光景だ。
滝と名付けるには多少無理があるが、本来の滝は下流50mの所にあるそうだ。
2016.12.3
2015.12.13
袋田の滝(茨城県大子町)
日本三名瀑に名を連ねるだけのことはある。
那智の滝や華厳の滝のような直瀑ではないが、高さ120m、幅73mの4段の段爆も決して引けを取らない。
4段の段爆、高さ120m、幅73m 2020.4.7
生瀬の滝(茨城県大子町)
袋田の滝の上にある滝。
落差は10m 2020.4.7
月待の滝(茨城県大子町)
案内看板には「日本一やさしい裏見の滝」とある。
熊本県小国町の鍋ヶ滝は幅が20mもある裏見の滝だったので、それと比較すればとてもやさしい感じがする。
幅12m、落差17m 2020.4.7
裏側から
丸神の滝(埼玉県小鹿野町)
小鹿野町の小森川上流のある滝で、日本滝百選にも選ばれている3段76mの段瀑。
道の駅両神温泉薬師の湯から車で20分、徒歩で15分。
2019.5.1
| 下からは見えないが上にあと2段瀑がある 見えている滝の長さは50m |
1段目12m、2段目14m、3段目50mの全長76m |
三条の滝(福島県檜枝岐村)
尾瀬を水源に持つ只見川の上流にある滝で、落差100mの直爆としては国内最大級の規模。
御池(みいけ)から尾瀬ヶ原に行く途中に立ち寄った。
秋でこれだけの水量があるんだから、雪解けの頃はいったいどれほどになるんだろう。
この上流には滑床の平滑(ひらなめ)の滝もある。
日本の滝百選にも選ばれている 2017.9.30
尾瀬を水源に持つ只見川の水量はすごい
黒檜沢(くろびさわ)の滝 2017.10.22
(福島県南会津町大桃)
華厳の滝、湯滝(栃木県日光市)
日光周辺には多くの滝があるが、その中でも最も有名なのが華厳の滝だ。
中学校の修学旅行で立ち寄ったような気もするが定かではない。
日本三名瀑の一つであり、中禅寺湖から流れ落ちる直爆は、同じ日本三名瀑の那智の滝に勝るとも劣らない。
また、湯ノ湖から流れ落ちる湯滝は、華厳の滝、竜頭の滝と並んで、奥日光三名瀑と呼ばれている。
| 華厳の滝 2013.10.13 日本三名瀑の一つで、落差は97m |
湯滝 2013.10.13
湯ノ湖から流れ落ちる落差50mの滝
奥日光三名瀑の一つ
浄蓮の滝(静岡県伊豆市)
伊豆市の湯ヶ島にある浄蓮の滝は、石川さゆりのヒット曲「天城越え」の歌詞にも登場する。
落差25mの直爆で、日本の滝百選にも選ばれている。
浄蓮の滝 2015.4.4
吹割の滝(群馬県沼田市)
この滝には3度も訪れた。
吹割の滝は片品川の渓谷にあり、上流の泙川に釣りに行った帰りに立ち寄ったのが最初。
次は新潟支店時代の社員旅行のときで、今回は帰省の帰りに立ち寄った。
川沿いに遊歩道が整備されており、中国語や韓国語のアナウンスも流れるなど、多くの観光客で賑わっている。
東洋のナイヤガラと称されているが、銚子の屏風ヶ浦が東洋のドーバーと称されるのと同じレベルだ。
高さ7m、幅30mの滝。 2016.8.17
ナイヤガラと比較するには無理がある?
震動の滝(大分県九重町)
大分県九重町にある震動の滝は日本の滝百選にも選ばれている、落差93mの雌滝と落差83mの雄滝からなる滝。
その姿は、観光名所になっている夢大吊橋から見ることができる。
| 雌滝 落差93m 2009.6.7 | 雄滝 落差83m(直爆) |
見返りの滝(佐賀県唐津市相知町)
佐賀県唐津市にある見返りに滝には二度ほど訪れた。
一度は6月のあじさい祭りの頃で、滝の周辺にはたくさんの色とりどりのあじさいが咲き、観光名所になっている。
落差100mの分岐爆で、九州一の落差を誇る滝は見ごたえ十分だった。
日本の滝百選にも選ばれている。
2011.9.19
2011.6.19
真名井の滝(宮崎県高千穂峡)
福岡に4年もいたので、九州各地の旅行ついでに立ち寄った滝も多い。
宮崎県高千穂峡にある真名井の滝もその一つ。
五ヶ瀬川に流れ落ちる滝は見事で、日本の滝百選にも選ばれている。
真名井の滝 2011.9.24
落差は17m
鍋ヶ滝(熊本県小国町)
熊本県小国町にある鍋ヶ滝は落差は10mと低いものの、幅が20mもあり、カーテンのように流れ落ちる水が印象的。
裏側からも見れる、裏見の滝になっている。
鍋ヶ滝 2011.9.25
裏見の滝になっている。
福岡の滝
福岡県と佐賀県の分水嶺である背振山系は、福岡側の方が急崖となっているので滝も多い。
室見川水系には、花乱の滝や坊主が滝、丁の滝を始め、名もない滝も多く見られ、沢登りも人気がある。
花乱の滝(福岡市早良区)
室見川の支流滝川にある落差15mの滝
2009.11.15
白糸の滝(糸島市白糸)
佐賀に抜ける長野峠の手前にある落差24mの滝
2011.6.26
清賀の滝(糸島市雷山)
千如寺から雷山への登山道沿いにある
2010.11.28
道明の滝(佐賀市三瀬村)
山中から金山への登山道沿いにある落差10mの滝
2010.5.4
丁の滝(福岡市早良区)
室見川野河内渓谷にある2段の滝
2009.11.14
坊主が滝(福岡市早良区)
室見川の支流坊主川にある落差14mの滝
2010.6.20
那智の滝(和歌山県那智勝浦町)
那智の滝は日本三名瀑の一つ。
ほとんど垂直に落下する直瀑で、落差は133mもある。
那智勝浦は大阪からはかなり遠いが、一度は見ておきたいと周辺の観光を兼ねて見に行った。
| 那智の滝 2008.11.2 |
箕面の滝(大阪府箕面市)
大阪時代は豊中市の千里中央に住んでいたので、箕面方面へはよく出掛けた。
日本の滝百選にも選ばれている箕面の滝は、紅葉の名所としても有名で、多くの人が訪れる場所でもある。
落差は33m。
箕面の滝 2008.5.17