佐渡の渓流Ⅱ
石花川取水口跡~小股沢
メインテーマ第三弾は、石花川の取水口跡から水路跡をイラツボ沢取水口跡~砥石沢取水口跡~ブイガ沢取水口跡
と通り、水圧鉄管上部の水槽(ヘッドタンク)跡を経由して小股沢の取水口跡から小股沢源流部を調査するというもの。
相当な距離を歩くことになるが、石花川発電所が廃止になったのは2016年とまだ5年しか経っておらず、青い等高線
と呼ばれるだけに、容易に通過できるものと信じて疑わなかった。
※砥石沢とブイガ沢に取水口があったかどうかは不明
石花川本流~堰堤
発電所跡に車を止め、堰堤上流にある取水口を目指して林道を進む。
26日に同じルートを目指して進んでいたが、取水口手前から冷たい霙混じりの雨が降りだし、イラツボ沢の取水口
跡あたりから本降りになったため断念していた。
戸地川に行った後、最後をどこにするか悩んだが、どうしても諦めきれなかったので、今回再挑戦となったもの。
本流は雪解けの水と前日の雨でかなり増水しており、竿を出せるようなポイントは少ない。
2、3ヶ所竿を出した後、増水した川を慎重に徒渉し堰堤上流に向かった。
| 石花川 |
増水で竿を出せるようなポイントは少ない | 本来ならこういう所がポイントなんだが |
| 17㎝のチビ山女魚 |
降海型の岩魚 | 堰堤までは山女魚と岩魚が混生する |
| 徒渉するのも困難なほど増水している |
チビ岩魚 | 20㎝を超える型のいい山女魚 |
堰堤上流~取水口跡
山女魚は堰堤までで、堰堤上流は岩魚領域になる。
渓相は落差のある好ポイントが続き、魚影もそこそこはある。
堰堤から400m程で取水口跡が現れる。
取水口跡の上流は右岸から長尾沢が出合い、更に棚山沢と松尾沢に分かれるが、取水口跡上流でまだ岩魚は
確認できていない。
| 堰堤上流 | 堰堤から上は岩魚領域になる |
水量が多く釣りにならない |
| 魚影はそこそこある | 落差のある好ポイントが続く | 取水口跡 |
水路跡~小股沢
イラツボ沢の取水口跡の上流を少し探って見たが、水量が多くアタリはなかった。
砥石沢もアタリはなかったが、沢自体が小さく魚がいる感じはしなかった。
前回砥石沢の取水口跡までは行っていたが、小股沢の取水口跡までは、その4、5倍の距離がある。
砥石沢を過ぎてからも順調に進んでいたが、ブイガ沢の手前300m程の所に来たら、いきなりトンネルが現れた。
トンネルは低く奥が深そうで、たとえヘッドランプがあったとしても、とても入る勇気のないものだった。
想定外の展開に動揺してしまったが、横に迂回路らしき道があったので、これを進んでみることにした。
道は荒れていて、ガレ場を慎重にトラバースしたと思ったら、その先が崩落。
強硬突破するにはあまりに危険なので、小さく巻こうと崖を木に掴まりながらよじ上るも巻けずに万事休す。
スワミベルトとザイルを取り出し、慎重にガレ場まで後ずさりして戻った。
諦めて戻ろうかとも思ったが、ガレ場を直登して左から大きく巻けば行けそうな気がした。
| 左岸にも水路跡らしきものがあるが、どこまで繋がっているのだろう | 右岸の水路跡をイラツボ沢へ向かう |
こんなものが何ヶ所かぶら下がっていたが、いったい何? |
| イラツボ沢の取水口跡 | 砥石沢の取水口跡 (砥石沢に取水口があったかどうかは不明) |
倒木や落石で塞がれたところもある |
| 突然トンネルが現れたが、かなり長いようだ | 迂回路のガレ場をトラバースし振り返る この崖の中をトンネルが通っているはずだ |
ガレ場を50m直登し、左から大きく巻いた |
ガレ場を50m直登し、左から大きく巻いて再び水路跡に出ることができたが、ここを通過するのに35分を要した。
ちょうど下りた地点がトンネルの出口の先だったことからも、このトンネルは50m以上はある長いものだと分かった。
崩落場所を確認するため迂回路を戻って見ると、最初の所を通過したとしてもまた直ぐに崩落していたのが分かった。
大きく高巻いて正解だったわけだ。
| 大きく巻いて再び水路跡に出た | 下りた地点がトンネルの出口付近だった | トンネルは長く、とても入る勇気はない |
| 迂回路を戻って見た | 崩落箇所 | 真下に壊れかけた迂回用の橋があった |
| 水路はこんな感じになっている | ブイガ沢の取水口跡 (ブイガ沢に取水口があったかどうかは不明) |
ブイガ沢 |
ブイガ沢の取水口跡からは快適な水路跡歩きが続き、水槽跡まで25分、水槽跡から小股沢の取水口跡まで20分で
到着することができた。
| 快適な水路跡歩きが続く | 水槽(ヘッドタンク)跡 | 水圧鉄管を撤去した跡 |
| 水槽跡からも快適な水路跡歩きが続く | 一輪車の残骸 | 小股沢の取水口跡 |
| 小股沢取水口跡 | 取水口跡の上から竿を出した |
直ぐに24㎝の良型が出た |
| 落差のあるポイントが続く | 大物がいそうな淵も連続する | 水量も多く申し分ない沢だ |
| これも24㎝の良型 | 今回は300m程しか竿を出さなかった | 左沢 |
帰りの林道は想像以上に荒れていて、人が歩くのもやっとという状態だった。
下から2番目の堰堤の上から左岸に渡り、沢沿いに下りて発電所跡に戻った。
7時に歩き始めて6時間半、もう限界に近かった。
| 沢沿いの林道は荒れ放題 | 崩落箇所も | 落石も |
| 下から2番目の堰堤の上から左岸に渡る | 沢沿いに下る | 一番下の堰堤 |
コースタイム
発電所跡7:00-堰堤上流8:00-取水口跡8:40-イラツボ沢取水口跡8:50-イラツボ沢8:50~9:20-砥石沢取水口跡
9:10-砥石沢9:10~9:25-トンネル高巻9:50~10:25-ブイガ沢10:35-水槽跡11:00-小股沢取水口跡11:20
-小股沢11:20~12:20-2番目の堰堤12:55-発電所跡13:35
6時間35分 2021.3.29
戸地川右俣~右俣取水口跡
メインテーマ第二弾は、戸地川右俣の魚止めの滝手前にある右岸のガレ沢を150m直登し、水路跡から上流の
取水口跡を目指すというもの。
戸地川の発電所が廃止になったのは1977年なので、既に40年以上は経過していることになる。
水路跡の状態が気になるところだが、ダメ元での挑戦だった。
まずは二俣から右俣を魚止めの滝手前まで竿を出して釣り上ることにした。
右俣~魚止めの滝
| 戸地川右俣 | チビ岩魚は活発にエサを追うが |
戸地川の水は冷たく澄んでいる |
| 左俣に比べ型も小さく、数も少ない | チビばかりでダメだなと油断していたら |
35㎝の尺岩魚が釣れた |
ガレ沢を直登する前に、魚止めの滝を見ておくことにした。
滝は手前に通らずがあるので、右岸の崖からしか見ることが出来ない。
通らずは左側にステップがあるが、たとえ通過できても帰りはドボン覚悟になるだろう。
ガレ沢の入口から右の斜面を上り、崖から写真を撮ることにした。
安全のためスワミベルトを装着し、セルフビレイしてからカメラを取り出し撮影した。
| 魚止めの滝手前にある通らず 夏なら泳いで突破できそうだが |
安全のためシュリンゲでセルフビレイする |
安全のためスワミベルトを装着 |
| 右俣魚止めの滝 上にも何段か繋がって見える |
滝は全部で七段あるそうだ |
ガレ沢~水路跡
ガレ沢は見た目以上に傾斜があり、ズルズルと岩ごと滑り落ちてなかなか進まない。
この日のためにヘルメットを新調したが、落石に注意しながら慎重に上った。
100m上ったところでとうとう息が切れたが、これ以上の直登は難しそうだった。
引き返そうとも思ったが、ここまで来て止めるわけにもいかない。
最後の50mは右から小尾根に取り付き、樹林帯を暫く進むと標高400mの地点でやっと水路跡に出た。
| 右岸のガレ沢を直登する | 見た目以上に傾斜がある |
50m程上ったところで振り返る |
| 100m上ったところで右の小尾根に取り付いた | 樹林帯を進む |
標高400m、水路跡に出た |
水路跡~取水口
40年以上も経つ遺構だけあって、水路跡はかなり荒れていた。
水路跡を覆った檜の枝を掻き分け、倒木を潜ったり乗り越えたりと、なかなかスムーズには進めない。
30分程歩いて白水川の取水口跡に到着。
白水川出合いから先は中ノ川と呼ぶようで、落差のあるポイントの連続に期待が膨らむ。
早速竿を出して見たがアタリはなく、取水口跡まで粘って見たものの反応はまったくなかった。
これだけの好ポイントなのにアタリがないのは、右俣は魚止めの滝が本当の魚止めなのかもしれない。
険しすぎて源頭放流も出来なかったのだろうか。
| 檜の枝を掻き分けて進む | 倒木は潜るか乗り越すかの何れかで突破 | 眼下に右俣の源流部が見えてきた 手前に滝が見える |
| 崩落して危ない場所もある | 40年以上も前の遺構 |
白水川の取水口跡 上った地点から500mの距離で30分掛かった |
| 白水川出合い上流付近 |
好ポイントが連続するがアタリはない |
白水川出合い下流付近 全く反応なし |
取水口跡からは戸地川第一発電所の水槽跡まで繋がる水路跡が続いており、67年間も佐渡金山に電力を
供給していた遺構に歴史を感じる。
作業小屋のようなものもあったようで、ヤカンや一升ビンなども散乱していた。
| 右俣取水口跡 | 対岸の水路跡 |
発電所の水槽跡まで繋がる水路跡 |
| 建物の跡だろうか。 | ヤカン |
一升ビン |
取水口跡~水路跡~二俣
帰りはガレ沢を上った所から更に200m手前の、429mの標高点下まで行き、檜のある尾根を下降して二俣に戻った。
帰りの水路跡もかなり荒れていて、行くとき以上に大変だった。
| 429mの標高点下の水路跡 | 檜のある尾根を下降する |
二俣の左俣側に下りた |
コースタイム
林道ゲート6:30-二俣6:55-右俣7:00~8:25-ガレ沢8:25-水路跡8:55-白水川取水口跡9:25-中ノ川取水口跡9:50
-429m標高点下11:05-二俣11:40-林道ゲート12:15
5時間45分 2021.3.27
山居池~大ザレ川~泊川
和木川、長江川と肩慣らしも終わり、いよいよ今回のメインテーマに移行。
第一弾は山居池から大ザレ川に下降し、山居道なるものを通って隣の泊川の源流を調査するという計画。
大ザレ川は昨年魚止めの滝まで調査済みだが、未調査の左沢を含めてもう一度竿を出して見ることにした。
前回は山居池の手前の沢を下降してしまったが、奥の沢に繋がる道が山居道であることが分かっている。
自宅を6時45分に出たが、山居池に着いたのは8時20分と、やはり真更川方面は遠い。
| 山居池入口 昨夜少し雪が降ったようだ |
山居池 左奥の斜面から下る |
山居池から繋がる山居道を下る 大ザレ川までの高低差は80m |
| 急斜面を沢に下りる | そのまま沢を下れば大オザレ川に出る |
大ザレ川 |
大ザレ川本流
川に下りて竿を出すと直ぐに釣れ出したが、どれも20㎝前後のチビばかりだ。
前回28㎝が釣れた3m滝でも不発に終わった。
| 釣れるのは20㎝前後のチビばかり | 朱点が鮮やかな岩魚だ |
最初の3m滝 |
| 3m滝で釣れた岩魚 | 前回28㎝が釣れた3m滝だが不発に終わる |
型が小さい |
滑床を過ぎると直ぐに魚止めの滝になる。
前回この滝壷で良型を含め6匹も釣れたので、期待が持てる最後のポイントだ。
滝は右岸から巻けるが、滝より上はザラ瀬で岩魚はいないと言う。
普段は釣り上げる度にリリースしているが、ここでは何匹釣れるか確認してから纏めてリリースすることにした。
子供は期待通りに次々と釣り上げ、あっという間に6匹になったが、どれも型は今一だ。
粘りに粘って7匹目に上げたのが28㎝の丸々と太った岩魚だったが、小さい順に釣れるというのが不思議で面白い。
さすがにもういないだろうと思いながらも、今度は私が竿を出すと何やら小さなアタリが...。
きっとチビ岩魚だろうと思いながらも粘っていたら、上がって来たのは何と33㎝もある尺岩魚だった。
| 滑床を進むともうすぐ魚止め滝だ | 前回6匹上げた魚止めの滝 果たして何匹釣れるのか |
7匹釣り上げたところでまとめてリリース |
| 子供が粘りに粘って釣った7匹目 28㎝だが丸々と太っていた |
さすがにこれで最後だと思ったのに | 8匹目に33㎝の尺岩魚が来た |
左沢
山居道を下降したところから300m程進むと、右岸から左沢が出合う。
本流との水量比は1:2といったところだろうか。
出合いから100m程で小さな滝が連続するが、岩盤を滑り落ちる流れの小さな窪みに岩魚は生息していた。
| 左沢 | 流れの小さな窪みで連続ヒット | 27㎝と型の良いのが釣れた |
| 左沢にも岩魚が生息していることを確認した | これより上流は未確認 |
大ザレ川~山居道~泊川
山居道と言ってもちゃんとした道があるわけではない。
国土地理院の地図を見る限り、山居池から下降した地点の先にある左岸の小さな沢から、左右二つあるコル
(鞍部)のどちらかを越していく感じだった。
右の標高450mと標高370mの間のコルを選択すれば、上り高低差80m下り70mとなり、左の標高450mと標高
460mの間のコルを選択すれば、上り高度差140m下り70mとなる。
左の方が高度差はあるが、より泊川の源流部に出られるので、計画は左のルートを選択することにした。
まずは左岸の小さな沢を進んだが直ぐに倒木が行く手を阻み、傾斜もきつくなってきたので右の斜面に取り付き
上部に抜けた。
イバラや蔓性の植物が多く、体が絡まって歩き辛い
左側の斜面は傾斜がきついので自然と緩やかな右へ右へと回り込むような形になり、当初の計画とは違った右
のコルに抜け出てしまった。
コルの向こう側は緩やかな斜面になっていて、ところどころにピンクのテープがあるのを発見し、しばらく進むと
今度は石仏を発見した。
間違って進んだ方が山居道だったわけだ。
最後は小尾根を下り、上り始めて45分で泊川に到着した。
| 左岸の小さな沢を上る この先右の斜面に取り付き右へ右へと進む |
コルから先はピンクのテープを頼りに進んだ | 石仏が現れた |
| 平坦な場所が300m程続き、最後は小尾根を下降した | 泊川に到着 |
No.29 泊川
泊川は大ザレ川同様、145ある佐渡の2級河川リストには載っていない。
河口に大滝がある大ザレ川は海から魚が遡上できないが、泊川も五段の滝があり海から遡上できない川の一つ。
地元の人による源頭放流のおかげなのか、上流部にも岩魚が生息しているとのことだった。
私自身もビクに入れた岩魚を滝の上に放流したことがあるが、岩魚の持つ生命力の強さには驚かされるものがある。
以前NHKの番組でやっていたが、大雨で出来た水たまりに取り残された岩魚が、蛇のようにクネクネと歩くように
脱出する映像は衝撃的だった。
泊川では帰りのことも考え1時間程しか竿を出さなかったが、それでも数多くの岩魚が顔を出し楽しませてくれた。
| 早速竿を出し遡行を開始する | 朱点の鮮やかな岩魚 | 食いが浅いのか珍しくバラシてばかり |
| 型が小さいが魚影は濃い | 一度バレても二度まで追うが、三度目はない | 釣れるのはチビばかりだ |
釣り始めて暫くはチビ岩魚ばかりだったが、落差のある渓相に変わった途端型が良くなりだした。
子供は珍しくバラしが多く、一度バレても二度まで追うが、さすがに三度目はない。
尺級を掛けたので私がタモ網で取り込もうとしたが、二人の呼吸がうまくいかずバラしてしまった。
500m程進んだ所で、すでに13時を回っていたので納竿とし、右岸の小沢から当初往路で計画していたルートで
戻ることにした。
| 落差のあるポイント | 段々型が良くなりだした | 26㎝の良型 |
| 朱点のない降海型のような27㎝の岩魚 |
ここで尺級を掛けたが、タモ入れに手間取り痛恨のバラシ | ここで納竿 この先の小沢を詰めて戻ることにした |
泊川~大ザレ川
帰りは右岸の小沢を詰めて、当初往路で計画していた左側のコルから大ザレ川に下降することにした。
いつもながら、元来た川を下って戻るという選択肢はないのが我々流。
大きな滝なんかが現れたら大変なことになるが、幸い直登できる小さな滝だけだった。
沢の源頭部に差し掛かった時、GPSで位置情報を確認しようとしたら、スマホがまさかのバッテリー切れ。
位置が確認ができなくなってしまったが、電波状態が良かったので、子供がGPSで位置を確認してくれ事なきを得た。
沢は右方向に延びていたが、左側の斜面の上がコルで、そこから下って行くのが正解だった。
帰りも45分掛かり大ザレ川に到着。
山居池までまた上らなければならないのが辛いが、帰りに大ザレの滝を見て帰りたかったので先を急いだ。
山居道は泊川から小河内川まで続いているとのことなので、機会があればまた挑戦してみたい。
| 沢の源頭部を右に行ってしまったが、左側にコルがあったようだ | 左の斜面を下降する |
大ザレ川左岸の小沢に出た。 |
コースタイム
山居池入口8:25-大ザレ川8:50-魚止めの滝9:50~10:15-左沢10:35~10:55-左岸の小沢11:00-石仏11:25
-泊川11:45-右岸の小沢13:10-大ザレ川13:55-山居池入口14:30
6時間05分 2021.3.23
大ザレの滝
山居池を後にし、大ザレの滝へと続く道のある柿畑に着いた時はすでに15時を回っていた。
柿畑から海までは100m程下るが、山居池~大ザレ川~泊川の上り下りを3セットもこなした後だけに辛い。
夕方までに両津の親戚に寄らなければならなかったが、足が思うように動かない。
海岸沿いも石がゴロゴロとしていて歩きにくく、もう疲労困憊だった。
柿畑から滝までは20分、帰りは30分も掛かった。
落差は70mと言われるが、実際に滝を登った人の記録を見ると、2段目の滝F2を合わせても48m程らしい。
2021.3.23
| 柿畑の横に海に下る道の入口がある | 海まで100m程下る(10分) |
滝までは海岸を500m程歩かなければならない(10分) |
| 大ザレの滝と海府大橋 | 実際の落差は40m程か |
白布の滝
「中川の上流字白布にあり、懸泉数丈の断崖を下る処白布をさらせるが如し、此名ある所以なり」
畑野村志より
旧畑野町小倉地区西ヶ平にある白布(しらふ)の滝。
その存在自体は前々から知っていたが、林道からの入口が分からず、まだ行ったことがなかった。
行った人のブログを見ると、水路沿いに道があり簡単に行けそうだったので、タウンシューズで出掛けたが、
結局入口が分からず、手は切るわ、レンズキャップは失くすわで散々だった。
西ヶ平は実家から15分も掛からないので、ちょっと出掛けてくる感覚だったが、やっぱり滝への入口が分からない。
結局荒れた林道を暫く進み、林道横に車を止めて、斜面から川に下りるしかなかった。
そこから川沿いを歩き、やっとのことで滝に辿り着いたというわけだ。
(帰りになってやっと入口が分かったのだが...)
2021.3.22
旧畑野町小倉にある白布の滝
3日後、再び白布の滝を訪れた。
失くしたレンズキャップの捜索がてら、今度は渓流タビを履いて水路沿いに行って見ることにした。
水路沿いの道はよく整備されており、途中からは川沿いを歩くことになるが、渓流タビなので川の中も平気だ。
結局レンズキャップは見つけることができなかったが。
2021.3.25
| 林道から水路へと続く道 前回はこれが見つけられなかった |
滝へと続く水路沿いの道 |
途中にある3m程の小さな滝 |
| 水路の取水口 | 川沿いを歩く |
前回はこの斜面をタウンシューズで下りて来た |
落差は20m程
早春の長江川
長江川は上流まで難所もなく面白みに欠ける川だが、標高450m付近の右岸の沢を詰め、金北山登山道から戻る
計画を立てていた。
今年はまだ雪が多く残っていたので早すぎる気もしたが、行けるところまで行って見ることにした。
まずは堰堤上流から入渓し竿を出して見たが、釣れるのは20㎝前後のチビ岩魚と冴えない。
雪解けで水量が多くポイント選びが難しい。
2021.3.22
| 堰堤上流から入渓 | 釣れるのはチビばかり | 雪解けで水量が多く、限られたポイントにしか竿を出せない |
| いかにも大物がいそうなポイントだが | なかなかサイズが上がらない |
キクバオウレン |
500m程進んだ所からやっと良型が釣れ出したが、霙混じりの冷たい雨が降り出したため沢詰めは諦め納竿。
| 上流に行くにしたがって型が良くなりだした | 26㎝~27㎝と良型が釣れ出した |
27㎝ |
| この日最大の28㎝ | 霙混じりの冷たい雨が降り出したため納竿 水量も多くポイントがなくなってきた |
帰りにお浸し用の山葵を少々持ち帰った |
早春の和木川
一日遅れでやって来た子供と、まずは肩慣らしにと和木川に入った。
受験勉強から解放され、1年ぶりの佐渡での釣りを満喫したいのだろう。
この日はあかねのラスト航行だったので、一等は満席だったようで、乗船客にはちょっとした記念品が配られたそうだ。
評判の悪かったあかねだが、とにかく揺れるらしい。
両津港で合流し、そのまま和木へと向かった。
林道石名-和木線にはまだ雪が残っていたので、下流から入渓することにした。
和木川の下流は堰堤だらけで釣趣に欠けるが魚影は濃い。
直ぐにレギュラーサイズ飛び出し、27㎝~28㎝の良型も顔を出してくれた。
2021.3.20
| 雪解けで水量が多い | 直ぐにレギュラーサイズが顔を出してくれた |
チビ岩魚も混じる |
| 藪のない3月は遡行し易い | まだサビが残る28㎝ |
27㎝の良型 |
右俣にも入って見たが水量が多く釣りにならないので、チビ岩魚1匹上げたところで納竿とした。
二俣から林道に出る際、雪の下の空洞に片足を取られ危なかったが、雪の斜面を歩く時は細心の注意が必要だ。
| 昨年に比べ今年は雪が多かったようだ | これも27㎝の良型 | 右俣は水量が多く釣りにならない |
| 雪に埋もれた林道を下る | フクジュソウ |
キクザキイチゲ |
続・祓川左俣
山や沢に入った後はGPSのログを確認し、実際に通ったルートを地図と照らし合わせながら記録している。
祓川の上流の滝を見て帰った後、いつものようにGPSのログを確認していると、滝の下流にあった落ち口がF2、5m
の滝ではないんじゃないかと自信が持てなくなってしまった。
ちゃんと確認すればよかったのだが、モヤモヤした気持ちのままで佐渡を後にしたくなかった。
F2さえ巻くことが出来ればそのまま今回調査した所を遡行し、二俣の左側の沢を詰めて、女神山から小倉峠に繋が
る林道へ出られるはずだ。
林道から小倉峠を経て、旧道から小倉トンネルまで戻る計画を立てた。
小倉トンネルの手前の駐車場に車を止め、斜面から沢に下りて遡行を開始。
最初から渓流シューズにスパッツで身を固め、スワミベルトに20mロープ、シュリンゲを持参して臨んだ。
遡行開始から15分、最初の滝、F1、5mに到着。
3月には右岸から大きく巻いたが、今回は左岸を小さく巻いた。
落ち口からロープを垂らして実測すると落差は8m程あり、目測のいい加減さを改めて痛感する。
| 渓流シューズにスパッツ | 装備はスワミベルトにエイト環、シュリンゲ 20mのロープも持参した |
小倉トンネルの手前の駐車場に車を止め、右の斜面を下りる |
| 棚田跡 滝から水を引いていたので、川沿いに棚田跡が続く |
F1、5mの滝 実測すると8mはあった |
今回は左岸から巻いた |
F1から20分でF2、5mの滝に到着。
まずは右岸の斜面を木の枝に掴まりながら巻いてみようと、急斜面を慎重にトラバースしながら進む。
太めの木の枝にシュリンゲでセルフビレイ(自己確保)しながらルートを探った。
あともう少しというところまできたが、枝と枝と間隔が広くなり、にっちもさっちもいかなくなってきた。
滑落のリスクが高いので強硬突破するのは諦め、20mロープを取り出した後、斜めに懸垂をしながら急斜面を
下りた。
今度は大きく高巻こうとガレ場を直登してみるが、30m、40mと高度を上げていっても、右側には直立した岸壁が
ずっと上まで続いていて、巻けそうな場所がない。
F2のすぐ上に滝が見えたが、先日見た滝かどうが判別がつかず、無念の敗退となってしまった。
| F1の上流 |
2mの滝 | F2、5mの滝 右岸の斜面を巻こうと試みた |
コースタイム
小倉トンネル駐車場7:20-F1、5mの滝7:35-F2、5mの滝7:55~8:40-小倉トンネル駐車場9:15
2020.11.14
張骨沢七つ滝
朝起きて外を見ると文句なしの快晴。
岨巒堂山に登るのを一日ずらせばよかったが、過ぎてしまったことを悔やんでも仕方がない。
ギアを上げて今度は七つ滝に挑戦しなければならない。
張骨沢は新保川の支流で、七つ滝を目指すには出合いの不動滝を巻くか、片辺ルートから下降するかの何れかだ。
片辺ルートは2006年の5月に一度途中まで行ってはいるが、沢は雪渓に覆われ滝の全貌はつかめなかった。
そもそも片辺ルートとは何なのかが分かっていない。
二の岳あたりを経由して外海府の片辺へ抜ける道なのだろうか。
金北山登山道の沢口コースは登山口の兵庫まで車が入れるが、荒れた林道を2駆の軽で上るのは不安がある。
初盛ダムに車を止めて歩くことにした。
| 初盛ダム(新保川第一堰堤) |
初盛ダムの奥に車を止めて歩行開始 |
九輪坊入口 |
| 水飲み場、梵字の滝 |
手前に穴があるが、夏は草で見えなかったのでうっかり足を落とし、膝と顔面を強打した | 沢口コースの登山口、兵庫 ここまで車で来れる |
歩き始めて45分で片辺ルートとの分岐に到着。
ここから又次郎川内沢を横切り、ミズナラの巨木があった開けた場所まで登る。
道はかなり荒れていて、何度か見失いそうになったが、ピンクのマーキングテープを探しながら進んだ。
| 落葉でフカフカの登山道を登る |
片辺ルートとの分岐 | 追分清水 |
| 又次郎川内沢を渡る | 荒れていて道が分かりづらい | ピンクのマーキングテープを探しながら進む |
| 標高670mの開けた場所に出た 倒れているのはミズナラの巨木だろうか |
枯れてしまったミズナラの巨木 2006年当時幹回り4m10㎝と書かれた看板が残っていた |
ピンクのマーキングテープはずっと続いているが、ここで引き返し沢に降りる |
ピンクのマーキングテープはずっと上まで続いていたが、ここで引き返し小さな沢沿いに下った。
最後は急斜面を慎重にトラバースしながら張骨沢の河原に降り立った。
直ぐに現れた2m滝を左岸から高巻き、更に50m程進むと、目の前には落差が10m以上はありそうな滝が姿を
現した。
これが七つ滝の最初の滝だが、左右見渡しても、右岸も左岸も巻けそうなところがない。
取り敢えず少し引き返し、左岸の涸沢を登ってみたが万事休す。
右の斜面に取り付き、開けた場所まで戻ることにした。
| 張骨沢の河原に降り立った ここで登山靴から渓流タビに履き替えた |
張骨沢を遡行 |
2mの滝 左岸を高巻く |
| 2mの滝の落ち口 | 透明度は抜群 | 姿を現した滝 落差は10m以上ありそうだ |
高巻きの途中、最初の滝の上にすぐ2番目の滝が見えたが、ここまで行くには難易度がかなり高そうだ。
もう少し作戦を練ってから再チャレンジすることにし、張骨沢を後にした。
| 高巻きの途中から見た滝 | 最初の滝の上にも滝が見える |
2番目の滝 |
| 追分清水のワサビ 年々減少しているのが気になる 大切にしたいものだ |
金北山の紅葉はもう終わりだ | 林道は予想に反して荒れてなかった |
沢口コース登山道から見る二箇沢三段の滝
初盛ダム
 |
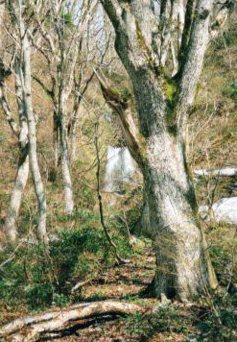 |
 |
| 2006年当時のミズナラの巨木 幹回り3m90㎝ (2006.5.3) |
これも2006年当時のミズナラの巨木 幹回り4m10㎝ (2006.5.3) |
2007年に神子岩から見た七つ滝 (2007.5.4) |
コースタイム
初盛ダム8:05-兵庫8:25-片辺分岐8:50-又次郎川内沢8:55-ミズナラ9:05-張骨沢9:25-滝9:50-ミズナラ10:10
-兵庫10:50-初盛ダム11:10
3時間5分 2020.11.12
祓川左俣上流の滝
朝起きると晴れていたので今度こそはと岨巒堂山へ向ったが、大佐渡は厚い雲に覆われたままだった。
同じ佐渡島内でも、国仲や小佐渡が晴れているのに大佐渡が雨というのも珍しいことではない。
急遽家に引き返し、計画を祓川に変更した。
祓川の左俣は今年の3月に遡行を試みたものの、F2、5mの滝に阻まれ上流の滝を見ることはできなかった。
今回は飯出山登山道を標高480mのピークまで行き、等高線の緩やかな斜面を下降し、川を滝のある所まで下る計画。
小倉トンネルの手前、七福神のある広場に車を止め登山を開始した。
昔の棚田跡が標高290mの水路跡まで続いているが、こんな奥まで開墾した小倉の人々の努力には感心させられる。
標高290mを過ぎると409mのピークまでは一気の登りとなる。
| 七福神のある広場 |
飯出山登山口 |
昔棚田のあった場所を登っていく |
| 佐渡の山に多いオオバクロモジ | 登山道ははっきりしていて迷うような所はない | 標高409mのピーク |
標高480mのピークまで進み、左側のやや緩やかな斜面を高低差80m程下ると、二俣に分かれた右側の沢に出た。
沢を100m程下った所で、二俣の左側の沢と合流。
ここで登山靴から渓流タビに履き替え川を下降した。
渓流シューズだと脱着するのが面倒だが、渓流タビは脱着が簡単で軽いので、持ち運びには便利だ。
二俣から300m程下ると、小さな滝が次々と現れ、標高330mの地点で10m程の緩やかに流れるような滝が現れた。
これが登山道から見えた滝で間違いないようだ。
この滝の下流に滝の落ち口らしきものが見えたが、これがF2、5mの滝だったのだろうか。
ちゃんと確認しなかったことが、のちのち後悔することになる。
帰りは左岸の涸沢を直登して標高460m付近の登山道に出た。
高低差130mの直登は結構しんどいものがある。
| 480mのピークからやや緩やかな斜面を下る | 二俣の右側の沢が見えた |
二俣右側の沢に下りた |
| 二俣左側の沢と合流 ここで渓流タビに履き替えた |
川を下ると3m程の滝が現れた | 小さな滝が連続する |
| これも3m程の滝 | 上流から4番目の滝 |
登山道から見えた滝に辿り着いた 長さは10m程だろうか |
体力的にまだ余裕があったので、水路跡を通って右俣の滝も見て帰ることにした。
水路跡は枝をかき分けて進まなければならないほど荒れていたが、川を遡行するよりは遥かに楽だ。
帰る頃にはとうとう雨になってしまったが、耐えられないほどのものではなかった。
| 標高290mラインにある水路跡 右俣の滝から棚田に水を引いていたようだ |
崖が崩れた危険な個所もある |
右俣の滝 落差は5m以上はありそうだ |
コースタイム
七福神広場7:30-標高470mピーク8:20-右の沢8:30-左の沢出合い8:35-左俣10m滝9:15-登山道9:40
-水路跡分岐10:05-右俣の滝10:35-登山道11:05-七福神広場11:25
3時間55分 2020.11.8
佐渡地域振興局地域整備部管内図
佐渡のすべての二級河川が記載された「佐渡地域振興局地域整備部管内図」を入手した。
竹田川ダムに流入する沢の名前が知りたくて、竹田川ダムをネットで検索していると、
佐渡地域振興局農林水産振興部と国府川左岸土地改良区という二つの組織が候補に出てきた。
まずは旧新穂村の瓜生屋にある佐渡地域振興局農林水産振興部の農地庁舎を訪問。
県の出先機関なので、役職者は島外から異動してきているのだろう。
(てっきり佐渡の人だと思ってベラベラ話をしたが、どうも話が噛み合わなかったので後から分かったこと)
応対してくれた職員に主旨を話すと、佐渡地域振興局地域整備部管内図なるものを出してきてくれた。
この地図には佐渡のすべての二級河川が記載されており、それ以外の沢も記載された優れものだった。
コピーだけでもと思っていたら、その場で相川にある地域整備部に掛け合って頂き、現物を頂けることになった。
残念ながら、竹田川ダムに流入する沢の名前は記載がなかったが、この地図を入手できたことは大きな収穫だ。
相川からの帰りに、旧畑野町寺田にある国府川左岸土地改良区に立ち寄って、竹田川ダムのことを聞いてみた
が、「そんなもん、分からんわさ」で終わってしまった。
佐渡地域振興局地域整備部管内図
和木川 右俣~左俣
右俣へは過去に2度入っているが、左俣を調査するのは今回が初めて。
まずは右俣から。
第一投から19㎝のチビ岩魚が掛かり、二投目に18㎝、三投目に23㎝と、小型主体ながら相変わら魚影が濃い。
| 左俣と右俣の分岐点 |
23㎝ |
水深20㎝程の所から飛び出してきた |
| 魚影は濃いが20㎝前後の小型が主体 |
こんな浅い所にもいるから侮れない |
23㎝ |
源流のため全体に型は小さいが、たまに大物も潜んでいるので侮れない。
今回もちょったした淵で強烈なアタリがあり、竿がグイグイと絞られた。
岩の隙間に逃げ込もうとするのを慎重にやり取りし、やっと姿を現したのは40㎝はあろうかと思える大物だった。
チョウチン釣りのため竿を縮めながら取り込もうとしたが、タモ入れに手こずり、寸前のところでハリス切れ。
逃がした魚は大きいと言うが、痛恨のバラシだった。
その後に29㎝の泣尺を上げたが、やはり引きが全然違った。
チョウチン釣りで大物を上げるのは難しい。
| この淵に29㎝が潜んでいた | 29㎝の泣尺 いい引きだった |
岩魚は岩陰から飛び出してくるから面白い |
| 最後に出た25㎝ |
標高500m付近からアタリがなくなる | 3mの滝 大物が居そうなポイントだがアタリはない |
左俣は出合いから300m程進むと石名-和木線の林道にぶつかり、金剛山(962m)の麓へと続いている。
水源を金剛山に持つためか、右俣より水が冷たく感じる。
出合いからすぐにチビ岩魚が顔を出し、幸先のいいスタートを切ったと思ったのもつかの間、すぐに堰堤が現れた。
堰堤より上流に岩魚がいる理由は二通り考えられる。
一つは釣り人が意図的に放流したもので、もう一つは堰堤ができる太古の昔より岩魚が棲みついていたと言うもの。
岩魚は氷河期の遺物と言われるように、水の冷たい山奥に陸封された魚なので、後者の説も有力だろう。
| 左俣 | すぐに堰堤が現れた | 堰堤で釣れた岩魚 |
| 堰堤上流 |
落差のある渓相が続く | 堰堤より上にも岩魚がいた |
持参したミミズが底をついたが、川虫が全然採れないのには参った。
やっとのことで捕まえた小さなオニチョロで、23㎝の型のいい岩魚を上げたところで納竿。
堰堤からしばらく進んだ土管のある場所だったが、地図をアプリに保存してなかったので現在地が分からない。
帰ってからGPSのログを確認したところ、林道と交差するすぐ手前まで来ていたことが分かった。
2020.9.2
| 土管のある場所で1匹上げたところで納竿 |
型のいい23㎝の岩魚 |
土管の奥に堰堤が見える |
和木川 右俣
法力和光滝を目指す途中竿を出しながら遡行したが、相変わらずチビ岩魚が盛んにアタックしてきた。
チビ岩魚の相手ばかりしていられないので、大きなポイントだけに絞ったが、昨年取り込みに失敗した所で42㎝
を取り込むことができた。
こんな小さな沢でここまで大きく育ったと思うと、感動せずにはいられなかった。
2021.6.16
| 何年生きてきたのだろう 50㎝になるまで生き延びていて欲しいものだ |
38㎝の丸々と太った岩魚 |
堰堤の岩魚と違って大きくなるのにも限界があるだろう |
| 30㎝の尺岩魚 | 31㎝の尺岩魚 | ちょうちん毛鉤 |
登攀用具
登攀と言っても、ハーケンを使うような本格的な沢登りをするわけではない。
沢を登るときに使用するわけではなく、専ら滝や崖を降りるときに備えて持参している。
5m程の小さな滝は直登か高巻きで突破できるが、降りるときには登攀用具が必要な時もある。
新規の川を調査するときは、必ずスワミベルトと6mm20mのロープを持参している。
急な崖を登るときはセルフビレイ用にスリングもあると安心だ。
スワミベルトを買ってからはハーネスを使うことが無くなってしまったが、大きな滝を下降するなら必要だろう。
大学釣部の頃は肩がらみだったが、今はエイト環を使うので懸垂下降も楽になった。
| 5mm10m、6mm20m、8mm20mのロープ 9mm以上でないとザイルとは呼ばないそうだ |
スワミベルトとエイト環 セルフビレイ用にスリングも持参している |
ハーネス 取り外しが面倒なので、釣りでは使っていない |
白瀬川 右俣~中俣~左俣
白瀬川は上流で3つの沢に分かれ、それぞれに発電所用の取水口があり、青い等高線と呼ばれる水路で繋がっている。
この水路を利用して、3つの沢を一気に調査するというのが今回の計画。
佐渡では珍しいくらい釣れない白瀬川だが、取水口付近なら釣れるのではないかという期待もあった。
発電所から1㎞ほどで林道は終点となり、そこから川に下りたが、連日の雨で川は想像以上の増水だった。
いくら増水していても居れば釣れないわけはないのだが、全くアタリがない。
川はすぐに3つに分かれるが、沢の名前が分からないので、左俣、中俣、右俣と呼ぶことにする。
水量比から見て右俣が本流筋になるようだが、増水による水勢が強く遡行できそうもない。
作業道が中俣に沿って続いていたので中俣に入ったが、ここも全くアタリがない。
出合いから200m程進むと作業道は沢から離れ、50m程登った所で標高340mラインにある水路に辿り着く。
左に進めば左俣の取水口で、右に進めば中俣の取水口となる。
中俣の取水口まで行っては見たが、取水口の上流も増水で遡行できそうもなかった。
| 東北電力白瀬発電所 |
白瀬林道終点 この先は作業道が続く |
増水した本流 |
| 中俣と右俣の分岐 | 右俣は増水で遡行できそうもない |
中俣 いかにも居そうなポイントだがアタリなし |
| 作業道を50m程登ると水路に辿り着く 標高340mラインに沿って続くので、青い等高線とも呼ばれる |
中俣の取水口 |
中俣の上流 ここも増水で遡行するのは難しい |
帰りに左俣にも少し入って見たが、ここでもアタリは全くなかった。
水が引いた後にもう一度調査することにして、今回はこれで一旦終了とした。
2020.7.13
| 左俣 |
水量は中俣と同じくらい |
ここでもアタリはなかった |
大雨から5日後、水が引くのを見計らって、再び白瀬川へと車を走らせた。
釣れない川だと分かっていても、中途半端に調査を終わらせるわけにはいかない。
最低限、まだ確認していない右俣と左俣の取水口だけでも見ておきたかった。
| 草が刈られ綺麗になった林道 |
林道終点 ここから作業道が水路まで続いている |
作業道も草が刈られ歩きやすい。 13日に来たときは草むらで道が見えなかった |
右俣
まずは右俣から遡行することにした。
まだ沢は増水ぎみだったが、遡行できないレベルではない。
念のため竿を出してみたが、やはりアタリはない。
これだけ大きな川なのに渓魚がいないのが不思議でならない。
雨が降ったせいもあるが、透明度があまり高くないのも気になるところ。
100m程進んだ所で、目の前に20mはあろうかと思える大滝が出現。
これはどう見ても高巻けないので、止む無く引き返し、作業道を水路へと登った。
右俣の取水口は小さなダムになっており、水路は標高340mラインに沿って、1㎞程先の水圧鉄管まで繋がっている。
| 右俣出合い付近 | 増水ぎみだが、遡行できないレベルではない | 突然目の前に大滝が出現 20mはありそうだ。これは高巻けない |
| 水路を目指して作業道を登る |
中俣の取水口から標高340mラインの水路を進む | トンネルと潜ると右俣の取水口が現れる |
| 右俣の取水口 ちょっとしたダムになっていた |
取水口から見た右俣の上流 | 水路は1㎞程先の水圧鉄管に繋がっている |
左俣
右俣から水路を引き返し、中俣の水路から左俣へ。
途中30mほどのトンネルがあり、中に5、6匹のコウモリがいたのには驚いた。
左俣は中俣同様落差のある険しい沢で、遡行は容易ではない感じだ。
右俣も中俣も左俣も、取水口より上は今回確認しなかったが、もしかすると岩魚がいるのかもしれない。
またいつか調査して見たいと思っている。
2020.7.20
| 中俣の取水口 | トンネルの先に左俣の取水口がある |
トンネルの中には5、6匹のコウモリがいた |
| 逃げ惑うコウモリ | 左俣の取水口 |
取水口上流の左俣 |
※後日、発電所を管轄する東北電力に確認したところ、右俣が馬の瀬川で、中俣が大平川、左俣が御林沢川、
そして、発電所下の左岸から流れ、同じく上流に取水口がある沢は立田沢川であると教えて頂いた。
ちなみに川の名前を調べる地図では中俣(大平川)が白瀬川の上流端となっている。
No.28 梅津川
梅津川はドンデン山と金北山の間にある山々を水源に持ち、両津湾に流れ出る川で、5,350mと佐渡では17番目に長い。
梅津川、水沢川、青竜川、大山川、御器清水川、大谷川と6つの支流を持ち、石花川の6つと並んで佐渡第2位を誇る。
昨年と今年の3月に、支流の水沢川と大山沢に入ったが、水川内沢に入るのは今回が初めて。
水川内沢は梅津川の本流筋になり、ドンデン山に続くアオネバ渓谷の登山道沿いにある。
発電所の取水口があるダムのバックウォーターから入渓。
1匹バラした後、20㎝、26㎝、24㎝と立て続けにきて期待が膨らんだが、堰堤を越えた途端ぱったりとアタリが止まった。
| 発電所取水口堰堤の上はちょっとしたダムになっている |
ダムのバックウォーターから入渓 |
すぐにアタリが来たが、痛恨のバラシ |
| 1匹バラした後、すぐに20㎝が来た |
続けて26㎝の良型 |
これも24㎝あった |
水量が豊富で渓相も抜群だが魚影すらなく、堰堤から40分程粘って見たが諦め、3m程の滝が出てきたところで納竿。
帰りは沢沿いの登山道を下って戻った。
2020.6.17
| すぐに堰堤が現れアタリが止まった | 渓相は抜群だがアタリはない |
水量は申し分ない |
| 居ないわけはないと思うのだが |
3mの滝が現れたところで納竿 |
アオネバ渓谷登山道入口 |
石花川 ルアー釣り
6月にもなると佐渡の渓流は藪に覆われ、入渓するのが難しくなる。
地元の釣具店でも、ミミズを置いているのは5月までで、6月以降は店頭から姿を消す。
ヘビが出る頃になると、渓流釣りをする人はいなくなるからだと言う。
そういう自分も最近は藪沢に入るのが億劫になってきた。
気分転換に、石花川の本流でルアーをやって見ることにした。
石花川の本流は大きな淵が連続し、チョウチン釣りでは仕掛けが届かない。
印西のWILD-1で買った、シンキングミノーを試しても見たかった。
発電所跡に車を止め、少し上った所から入渓。
手始めに、普段使っているブレットンのスピナーでキャストすると、すぐに20㎝の岩魚がヒットした。
この淵で30㎝の尺岩魚がヒット
スピナーにヒットした30㎝の岩魚、スピナーはブレットンの黒3.2g
| 石花川の本流は深い淵が連続する | 第一投目から20㎝の岩魚がヒットした |
その後も立て続けに6匹程スピナーにヒット |
その後も立て続けにスピナーにヒットしたが、6匹程上げた後はシンキングミノーに替えてチャレンジした。
試したシンキングミノーは、スピアヘッド・リュウキの50Sヤマメ4.5g。
1個1,000円もするものなので、木に引っ掛けないよう慎重にキャストした。
こちらも第一投目からヤマメがヒット。
ヤマメにヤマメじゃあ共食いだが、夏の渓流魚の活性の高さは驚きの連続だった。
大きな淵で32㎝の尺岩魚が掛かったが、ランディングさせた直後に、ロッドはポッキリ折れてしまった。
シンキングミノーに替え、これからというところだったが、ルアー釣りはこれにてThe End。
キラクのSP5EXは、大学生の頃から使っているロッドなので、劣化が激しくもう限界なのだろう。
手賀沼でブラックバスを掛けた時に一度折れてしまったが、SP6EXと合体させて修復したのに残念だ。
その後はエサ釣りに替えてみたが、小型岩魚ばかりで冴えなかった。
2020.6.8
この淵で32㎝の尺岩魚がヒット
シンキングミノーにヒットした32㎝の岩魚
スピアヘッド・リュウキ50Sヤマメ4.5g
| 佐渡で最も渓流らしい川と言われる石花川 |
ヤマメにヤマメがヒット |
シンキングミノーの威力も抜群だ |
ロッドが折れ、不完全燃焼で終わったルアーだが、家に戻ってから、穴釣り用のコンパクトロッドがあることに
気づいた。
もう1個のシンキングミノーもまだ試してなかったので、再び石花川へ。
前回よりも下流の、小股沢出合いから釣り始めることにした。
ミノーにもスピナーにもよくヒットしたが、出てくるのは小型ばかり。
その上、この日釣れた魚の半分以上がヤマメだった。
あわよくば大物をと期待していたが、そうそううまくはいかないものだ。
2020.6.10
佐渡で最も渓流らしい川と言われる石花川本流
シンキングミノーにヒットしたヤマメ
スピアヘッド・リュウキ50S MPテネシーシャッド
こういう場所はルアーやテンカラでしか狙えない
| 小股沢出合い付近から釣り始めた | すぐにシンキングミノーに岩魚がきたが型が小さい | ルアーにはもってこいのポイント |
| 本流にはヤマメも多い 釣れた魚の半分以上がヤマメだった |
ブレットンの赤3.2gにもよくヒットした | でも出てくるのは小型ばかり |
エサ釣りにも、型は小さいが、ネイティブなヤマメがたくさん顔を出してくれた。
石花川でヤマメが釣れるのは、戸地川と同じように途中に堰堤がなく、海からサクラマスが遡上できるからだろう。
堰堤だらけの川だとこうはいかない。
No.27 石花川 竹平沢
石花川には、小股沢、ブイガ沢、竹平沢、砥石沢、イラツボ沢、石花川の6つの支流があるが、竹平沢を調査する
のは今回が初めて。
出合いから100mほどで大きな滝となるので、竿を出せるポイントは僅かしかないが、岩魚がいることは確認した。
帰りに砥石沢も覗いてみたが、この沢は他の沢に比べ水量が極端に少なく、未調査ながら期待できそうもない感じだ。
2020.6.10
| 竹平沢出合い | 滝までの僅かなポイントで、複数の魚影を確認 | 竹平沢で出たチビ岩魚 |
| 出合いから100m程で滝になる |
竹平沢の滝 | 砥石沢 水量が少なく期待できそうにない |
石花川 ブイガ沢
ブイガ沢は前回、出合いから滝まで岩魚がいることを確認したが、滝より先は未確認だったため入って見ることにした。
前回同様、出合いから滝までの僅かな間で岩魚や山女魚が釣れたが、水深20㎝にも満たない所から飛び出してきた
のには驚いた。
| ブイガ沢出合い | 24㎝の良型だ |
手前の瀬からヤマメが飛び出した |
| ヤマメも混じる |
こんな浅い所にもいるから侮れない | 岩魚の生命力には感心する |
滝をどう巻こうか考えていたが、直登できそうだったので途中まで登って見たが、上部がヌルヌルで結構危なかった。
滝から上も小さな滝が連続。竿を出しながら遡行していったがアタリが全くない。
40分程粘っては見たが諦め、標高280m付近で納竿。標高330m付近にある取水口跡まで行くのは諦めた。
滝を登るのは難しくないが、3mの滝でも掴まるものがないと降りるのは危険で難しい。
下りはロープを取り出し、危険なところは懸垂で降り、5mの滝は左岸を高巻いて降りた。
2020.6.8
| 5mの滝は右岸を直登した 上部がヌルヌルで掴まる木も細く危ない |
小さな滝が連続する | いかにも居そうなポイントだがアタリはない |
| 2mの滝 |
この滝は登るのは簡単だが、降りる時は掴まるものがなく危ない |
危ない所は懸垂で下降した |
石花川 長尾沢
石花川は取水口跡の上流で、長尾沢、松尾沢、棚山沢の3つの沢に分かれている。
取水口跡から200m程進んだ所で、左から長尾沢が出合い、更に200m程進んだ所で松尾沢と棚山沢に分かれる。
川の名前を調べる地図では長尾沢がイラツボ沢になっているが、佐渡トレッキング協会のマップの方を採用した。
本流筋は左岸から出合う棚山沢になるのだろうか。
長尾沢は地図を見る限りイラツボ沢同様に奥が深く、相当険しい沢のように見える。
出合いから100m程進むと予想通り5m程の滝が現れた。
左岸手前の尾根から巻くようだが、時間がなかったので引き返し、本流を少し上ったあとイラツボ沢へ向かった。
長尾沢は出合いから竿を出しながら遡行したがアタリはなく、本流上流も魚影は確認できなかった。
松尾沢と棚山沢はまた別の機会に改めて調査することにした。
2020.3.9
| 本流上流にある取水口跡 ここから水路がイラツボ沢へと繋がっている |
取水口跡上流 |
竿を出してみたがアタリがない |
| 右岸から出合う長尾沢 |
すぐに落差のある沢になってきた |
2m程の滝の奥に更に大きな滝が見える |
| 出合いから100m程で5mの滝が現れた | 本流上流 |
この先で松尾沢と棚山沢に分かれる |
和木川
右俣に岩魚が棲息していることは、3月の調査で確認済みだが、今回は右俣を標高650m付近にある法力和光滝まで
詰め、林道和木-石名線で戻る計画。
和木川は堰堤が多く遡行しづらい川だが、二俣より上流には堰堤がない。
二俣の手前から入渓して竿を出すと、第一投目から18㎝のチビ岩魚だ飛び出した。
二投目にも19㎝が来て、小型ながら相変わらず魚影の濃い川だ。
左俣にも少し入って見たが、確りと岩魚が棲息していることを確認。
二俣からは水量が二分され細流となるが、水深30㎝にも満たないポイントから、次々と岩魚が顔を出した。
| 二俣の手前から入渓 左俣と右俣で水量はほぼ半々 |
第一投目から18㎝のチビ岩魚だ飛び出した | 左俣にも少し入って見た |
| 左俣で釣れた岩魚 | 水深30㎝にも満たない小さなポイントにも確りと岩魚が居ついている |
小さなポイントから次々と岩魚が顔を出す 20㎝前後の小型が多い |
チョウチン毛鉤にも初めて挑戦した。
仕掛けは海釣り用の3号ライン1.5mに、毛鉤を直結した単純なもの。
最初はタイミングが合わずバラシが続いたが、1匹掛けた後はコツをつかみ、次々に掛けていった。
毛鉤は知人からもらった、クモかコガネムシに似せた変なものだったが、活性が高かったのか岩魚はこれに
よくヒットした。
| こういう場所は毛鉤で狙いやすい |
チョウチン毛鉤第一号 | クモかコガネムシに似せた変な毛鉤だがよくヒットした |
| 毛鉤に飛びつく瞬間がよく見えるポイント |
面白いように毛鉤に飛びついてきた | 毛鉤で6匹程掛けたので、初めてにしては上々の出来か |
標高500mを過ぎたあたりから沢は険しくなり、標高580mの所で落差が15m程ある滝が現れた。
左岸を巻こうと途中まで登っては見たが、斜面はズルズルで、掴まるものもなかったため、残念ながら法力和光滝
まで辿り着くことは叶わなかった。
単独釣行に無理は禁物だ。
2020.6.5
| こんな小さなポイントから31㎝の尺岩魚が飛び出してきたから油断ならない |
31㎝の尺岩魚 |
これも型のいい岩魚 |
| 標高500mを過ぎるあたりから険しくなってきた | 3mの滝。 | 標高500mを過ぎるとアタリがなくなった |
| 標高580m付近で現れた滝 |
流木の右から巻けそうだったが、斜面がズルズルで掴まるものもなかったため断念 |
3段で15mはあるだろうか |
No.26 石田川
石田川は大佐渡の地獄谷を水源に持ち、旧佐和田町の石田を経て真野湾に流れる出る川で、長さは7,000mと佐渡
では9番目に長い。
昨年藤津川で出会ったH老人の話では、一度入って見たが岩魚はいなかったと言われたが、一応この目で確かめて
見ることにした。
林道地獄谷線に架かる橋の所から斜面を下りて入渓。
暖冬の影響なのか水量は少なかったが、大佐渡の山から流れ出る川にしては水温が高く、薄茶色に濁っている。
水の色が以前入った中津川や地持院川の色に似ているのが気になる。
早速竿を出してみたがアタリはなく、40分程標高570m付近まで粘って見たが魚影すらなかった。
下流部は未調査だが、あまり期待できない川のようだ。
地獄谷という水源が良くないのかもしれない。
2020.6.3
| 林道地獄谷線に架かる橋 | 暖冬の影響なのか水量は少ない | 水の色が薄茶色に濁っているのが気になる |
| アタリが全くない |
標高570m付近で納竿 |
地獄谷線から見る雲海の国仲平野 |
小倉川支流 祓川左俣~右俣
飯出山に登った際にいくつかの滝が見えたが、気になってしょうがないので調査することにした。
まずは小倉トンネルの駐車場から斜面を下りて左俣を遡行。
出合いから900mほど上流にあるF1、5mまでは前回調査済みだが、新たな滝はその上流にあるはずだ。
F1は右岸から巻いて下り、30分ほど進むと5mの滝(F2)が現れた。
一瞬これが登山道から見えた滝かと思ったが、どうも形状が違った。
(去年登山道から見えた滝は3段くらいに連なる滝だった。)
更に上に滝があるようだが、F2を巻くのはかなり厄介そうだったので、左俣の調査は今回はここまで。
帰りはF2左岸手前の斜面を409mのピークまで直登し、飯出山の登山道経由で戻ることにした。
高低差は120m程だが、急斜面と新雪に足を取られ何度も滑り落ちそうになる。
木の枝に掴まりながら20m登っては休み、国土地図のアプリで位置を確認しながら、30分掛けてやっと登り切る
ことができた。
2020.3.6
| 出発点、小倉トンネル入口 駐車場に車を止め、斜面を下りて沢に出る |
祓川左俣 右俣との水量比は1:2といったところ |
F1、5m 5m以上はあるかもしれない。 (3m、5m、10m、15m、20mと大雑把にしか区分していない) |
| 高巻き途中から見たF1 滝壺で1匹バラシたので、僅かには棲息しているようだ |
F1の上に2mの小さな滝が現れる |
F2、5m 昨年登山道から見えた滝と形状が違う この上にまだ滝がいくつもあるということか |
| 高低差120mの急斜面を木の枝に掴まりながら登る |
もう少しで登山道に出るはず 眼下に小倉ダム(朱鷺湖)が見える |
409mのピーク、飯出山の登山道に出た |
登山道を登山口まで下り、今度は右俣を調査することに。
右俣は堰堤より先に入ったことは一度もなく、今回が初めてだったので最初から竿も出して遡行した。
渓相はいいのだが、1時間ほど竿を出しても全く反応がない。
堰堤から1㎞ほど進んだところで10mの滝が現れたが、これも昨年登山道から見えた滝と形状が違った。
(昨年見えたのは5段くらいの滝だった。)
滝は右岸に巻き道があり少し上まで行って見たが、体力も限界に近づいてきたのでここで終了とした。
帰りは滝から標高290mラインに沿って続く作業道らしきものがあり、30分程進むと再び飯出山登山道に合流した。
田んぼに水を送る水路として利用していた作業道なのだろうか。
| 祓川右俣 渓相はいいが全く反応がない |
F1、3m |
F1を越えると目の前に大きな滝が見えた 手前の淵でチビ岩魚を初めて確認 |
| F2、10m 右岸に巻き道と送水に利用していたと思われる塩ビ管の跡があった |
F1上流100m付近 |
滝から標高290mラインに沿って作業道らしきものがあった |
| やがて作業道は飯出山登山道に合流する |
再び登山口に到着(今日2度目) | 小倉トンネル入口の駐車場から見た飯出山 |
No.25 石花川 イラツボ沢
イラツボ沢は石花川にある6支流の一つで、石花林道終点の先にある堰堤上で右岸から出合う。
川の名前を調べる地図では砥石沢になっているが、佐渡トレッキング教会のマップではイラツボ沢になっている。
トレッキングマップではイラツボ沢の水源地がイラツボのコルとなっていたので、こちらの方を採用することにした。
長さは300mとあるが、ブイガ沢同様実際は奥が深く1,000m以上はある。
本流上流の340mのラインと平行して発電所の水圧鉄管跡まで水路跡があり、イラツボ沢、砥石沢、ブイガ沢と
繋がっている。
今回は本流の取水口跡から水路跡を進みイラツボ沢を下降したが、取水口跡より奥も水量は豊富で面白そうな
感じだった。
次回は砥石沢から上り、イラツボ沢の奥を調べてみようと思っている。
2020.3.9
| 本流の取水口跡から水路跡沿いをイラツボ沢へ進む | イラツボ沢の取水口跡 水路跡は砥石沢からブイガ沢へと続く |
取水口跡上流部 かなり奥まで行けそうだ |
| イラツボ沢 |
イラツボ沢はチビ岩魚が2匹出ただけだった | イラツボ沢出合い |
No.24 石花川 ブイガ沢
ブイガ沢は石花川にある6支流の一つ。
長さは300mとあるが、実際は奥が深く1,000m以上はある。
河川法で定める川の長さは人が管理する所までだろうから、300mというのはきっと取水口跡あたりまでの距離だろう。
今回は出合いからすぐに見える5mの滝までしか行っていないが、300m上流には発電所があった頃の取水口跡がある。
次回は滝を巻いて取水口跡の上流を調べた後、帰りは水路跡を小股沢の取水口跡まで行き、小股沢上流部を調べ
ようと思っている。
2020.3.9
| ブイガ沢 すぐ上に滝が見える |
ブイガ沢でも岩魚の棲息を確認した 24㎝だったが丸々と太っている |
ブイガ沢の滝、5m |